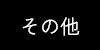食卓にリズムが生まれる大中小の
片口3兄弟
片口3兄弟

「ちょっといい気分」の原体験を
器に込めました
器に込めました
このたび『hibi hibiの台所』という本が生まれました。日々、美味しく食べていると暮らしが豊かになっていく私のときめきを、四季を感じつつ、晩酌という時間を楽しみつつ、皆さんと共有できたら……と綴った本です。その出版を記念して、器を作ろうと思いました。思い浮かんだのは、小さな片口の器。
結婚して生活道具を揃い始めた頃に手にしたのが、その小さな片口です。お店の屋根裏のような2階にぎっしりと器が並べられていた中から、目があったのがご縁。「珈琲時間のミルク入れにしましょう」。そう思って手にしました。それまでは珈琲を飲む傍らに牛乳パックをデデンと置いていたけれど、片口で空気がガラリと変わり、心地よさに包まれました。注ぐ楽しさなんかも感じられて。ほんの少しの行為で、ちょっといい気分になる体験をしたのです。
以来、片口の器にちょっとおかずを盛るのも好きになり。「ちょこっとキムチ」を、「個人盛りでおひたし」をというぐあいに楽しんでいました。さらに「フライにつけるタルタルソースをたっぷり入れてもいいなぁ」とあれこれ胸を膨らませ、大きさによって使い分けできるよう、まるで兄弟みたいな、大中小の3つのサイズをそろえた 『おかずを盛る小鉢のような片口の器』を作ることにしました。
結婚して生活道具を揃い始めた頃に手にしたのが、その小さな片口です。お店の屋根裏のような2階にぎっしりと器が並べられていた中から、目があったのがご縁。「珈琲時間のミルク入れにしましょう」。そう思って手にしました。それまでは珈琲を飲む傍らに牛乳パックをデデンと置いていたけれど、片口で空気がガラリと変わり、心地よさに包まれました。注ぐ楽しさなんかも感じられて。ほんの少しの行為で、ちょっといい気分になる体験をしたのです。
以来、片口の器にちょっとおかずを盛るのも好きになり。「ちょこっとキムチ」を、「個人盛りでおひたし」をというぐあいに楽しんでいました。さらに「フライにつけるタルタルソースをたっぷり入れてもいいなぁ」とあれこれ胸を膨らませ、大きさによって使い分けできるよう、まるで兄弟みたいな、大中小の3つのサイズをそろえた 『おかずを盛る小鉢のような片口の器』を作ることにしました。


影に邪魔されず、お気に入りの料理が、コロンと並ぶ
料理を器に盛り付ける時間は、気分が上がります。なのに、おかずに器の影が映ってしまうと、あぁ…と少しだけ残念に想うこともあって。窯元さんに、影ができないような形状にしていただきました。それから、高台(お茶碗などの底に付いている台)のある器ばかりが食卓に並ぶと、宙に浮かぶような景色も気になっていたので、高台をできるだけ目立たなくして、食卓にコロンと置くデザインに。
最初は1サイズで考えていましたが、大中小とあったら食卓の景色がいろいろ楽しめるなぁと(ワクワク)。食卓の真ん中にメイン料理を盛った大サイズの片口、2人家族なら中サイズにそれぞれに副菜を入れても。例えばチキンカツをのせた手持ちの平らなプレートに、酸っぱいソースを入れた小さな片口を合わせるのもいい!ですよね。大サイズでも直径12cmと中どんぶりのイメージです。重ねると入れ子みたいで、これまた可愛い(笑)。
今回は器をイメージしたイラストにメッセージを添えたオリジナルのカードもお入れしています。
ほっこりしていて、器にぴったりのカードになったなと思っていますので、どうぞ楽しみにしていてください。
3サイズセットはオリジナルデザインの化粧箱にお入れしてお届けします。
最初は1サイズで考えていましたが、大中小とあったら食卓の景色がいろいろ楽しめるなぁと(ワクワク)。食卓の真ん中にメイン料理を盛った大サイズの片口、2人家族なら中サイズにそれぞれに副菜を入れても。例えばチキンカツをのせた手持ちの平らなプレートに、酸っぱいソースを入れた小さな片口を合わせるのもいい!ですよね。大サイズでも直径12cmと中どんぶりのイメージです。重ねると入れ子みたいで、これまた可愛い(笑)。
今回は器をイメージしたイラストにメッセージを添えたオリジナルのカードもお入れしています。
ほっこりしていて、器にぴったりのカードになったなと思っていますので、どうぞ楽しみにしていてください。
3サイズセットはオリジナルデザインの化粧箱にお入れしてお届けします。

育てがいあるhibi hibiデザイン
形はコロン、表面はツルンとした手触り。こっくりした表情は、粉引き(こひき)という技法を使っているからなのだそう。何よりご縁を感じたのが、罅(ひび)が入ったような模様です。だって『hibi hibiの台所』ですから。焼き上がった陶器を冷ます過程で、陶器本体と釉薬の収縮率の違いによって生まれる現象なのだとか。“貫入(かんにゅう)”というそうです。一つひとつ違う、自然が描くデザイン。もちろん汁が漏れることはありません。使いこむほどに味わいが増していくのが特徴だそうです。時間が経つほどに愛着が湧く片口の器、大切に育てていきたいです。
じゃんじゃん、盛り付けを楽しもう!
おかずを盛って、薬味を添えて、
食卓が「ちょっといい気分」
食卓が「ちょっといい気分」

それでは、我が家の片口3兄弟の活躍ぶりをご紹介しましょう。直径9cmの中サイズに料理を盛り付けたときは、「おぉ」と感動してしまいました。なめこおろしとか、もずくの酢の物とか、形がとどまらないおつまみも素敵な姿です。もちろん、影に隠れることもありません。蒸籠の蓋がきちんと閉まる5cmほどの高さにしていただいたのもポイントで、茶碗蒸しも楽しみ。

直径12cmの大サイズに前日の残り物の煮物を入れたら、上品に整いました。「魯肉飯(ルーローハン)のミニ丼も似合うのではないか」とイメージしています。

そして末っ子、直径5cmほどの小サイズはソースや薬味がお似合い。我が家では塩焼きそばに黒酢を添えていますが、珈琲ミルクならこのサイズがぴったりですね。おちょこの風情も漂わせて、お酒にも良いかもと誘われております。
そこにあるだけで、ちょこんと片口があるだけで、食卓に遊び心が生まれて楽しくなります。
そこにあるだけで、ちょこんと片口があるだけで、食卓に遊び心が生まれて楽しくなります。
どんな日も好い日になる、「ちょっといい」積み重ね
始まりは一日一食の手作り弁当から
私は幼い頃から、アニメーションの中でも生活感のあるお家のシーンが好きでした。といっても、実際はていねいな暮らしではなく外食やコンビニに頼りっきりの時期も。「一食ぐらいは手作りのものを食べよう」とお昼のお弁当作りを始めたのがきっかけで、少しずつ今に行き着きました。
本やVlogでは、道端で積んだ草花を生けましたとか日々の小さな楽しさをご紹介しているのですが、「ていねいな暮らしですね」とコメントをいただくことが多く驚きました。私がイメージする“ていねい”は、時間をかけてお出汁をひいたり、毎日ぞうきんで床掃除をしたり。ささやかな楽しさを“ていねい”と受け取っていただいたんだなぁと。
『hibi hibi』の名前の由来は、禅語の『日々是好日』。ちょっといいことや、ちょっといい気分を、日々、積み重ねていくことで、どんな日でも好(よ)い日になるという想いを込めています。
『おかずを盛る小鉢のような片口の器』が、皆さんのhibi hibiに「ちょっといい」をもたらすことができたら、とても嬉しいです。
本やVlogでは、道端で積んだ草花を生けましたとか日々の小さな楽しさをご紹介しているのですが、「ていねいな暮らしですね」とコメントをいただくことが多く驚きました。私がイメージする“ていねい”は、時間をかけてお出汁をひいたり、毎日ぞうきんで床掃除をしたり。ささやかな楽しさを“ていねい”と受け取っていただいたんだなぁと。
『hibi hibi』の名前の由来は、禅語の『日々是好日』。ちょっといいことや、ちょっといい気分を、日々、積み重ねていくことで、どんな日でも好(よ)い日になるという想いを込めています。
『おかずを盛る小鉢のような片口の器』が、皆さんのhibi hibiに「ちょっといい」をもたらすことができたら、とても嬉しいです。
hibi hibi utsuwaの生まれたところ
hibi hibi utsuwaは茨城県の笠間市で生まれました。笠間焼は250年の歴史ある焼き物なのに、伝統的な技法に縛られない自由な表現が魅力なのだそうです。
『おかずを盛る小鉢のような片口の器』はわたしのデザインや希望を笠間焼の窯元“向山窯”の伝統工芸士の方が形にしてくれました。
焼き上がりの風合いや化粧の仕方など何度も試行錯誤してくれて行きついた、温かみのある手作りの器をどうぞ楽しんでください。

器に見られる斑点は、「御本手(ごほんで)」という陶器の装飾の一つです。焼成中に窯の環境によって器に自然に現れる表情で、萩焼や高麗茶碗にも使われる技法だそうです。
焼成中に土に含まれた鉄分が様々に反応し、この斑紋が現れます。現れ方の個体差は、窯のどの位置に入っていたか、その日の気温や天候などによっても変化するそうで、一つとして同じ表情はありません。どんな表情の子が届くのか楽しみにしていてください。

焼き上がった陶器を冷ます過程で、陶器本体と釉薬の収縮率の違いによって生まれる現象だそうです。
こちらも一つとして同じ表情はなく、使いこむほどに風合いが滑らかに変化していくと言われています。
hibi hibi utsuwaは、使いながら育てていく器です。お手元に届いた器の個性を愛でて、使ううちに現れる表情や手触りの日々日々の変化をどうぞ楽しんでください。
『おかずを盛る小鉢のような片口の器』はわたしのデザインや希望を笠間焼の窯元“向山窯”の伝統工芸士の方が形にしてくれました。
焼き上がりの風合いや化粧の仕方など何度も試行錯誤してくれて行きついた、温かみのある手作りの器をどうぞ楽しんでください。

器の表情について
器に見られる斑点は、「御本手(ごほんで)」という陶器の装飾の一つです。焼成中に窯の環境によって器に自然に現れる表情で、萩焼や高麗茶碗にも使われる技法だそうです。
焼成中に土に含まれた鉄分が様々に反応し、この斑紋が現れます。現れ方の個体差は、窯のどの位置に入っていたか、その日の気温や天候などによっても変化するそうで、一つとして同じ表情はありません。どんな表情の子が届くのか楽しみにしていてください。

焼き上がった陶器を冷ます過程で、陶器本体と釉薬の収縮率の違いによって生まれる現象だそうです。
こちらも一つとして同じ表情はなく、使いこむほどに風合いが滑らかに変化していくと言われています。
hibi hibi utsuwaは、使いながら育てていく器です。お手元に届いた器の個性を愛でて、使ううちに現れる表情や手触りの日々日々の変化をどうぞ楽しんでください。
- ▪再販予約期間:2025年8月1日(金)10:00~2025年8月25日(月)23:59
- ▪お届け予定日:発売日以降、順次発送いたします。
4件あります
4件あります