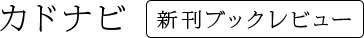戦後の闇市から世界有数の電気街へと発展した秋葉原は、一九九〇年代に入ると、オタクの街へと変容して現在に至っている。西條奈加の書き下ろし連作長篇は、その今の秋葉原を舞台にした、ファンタスティックなミステリーだ。
秋葉原の中央通りを西に折れ、蔵前橋通りに面したところにある先留交番。実際は駐在所で、権田利夫というブサメンのオタク警官が居座っている。そこに転がり込んできたのが、奥多摩の駐在所に勤務していた向谷弦だ。イケメンだが下半身が緩く、おまけにボケナスの向谷は、女性問題で謹慎処分となり、先輩の権田を頼ってきたのだ。さらに向谷には霊感があり、奥多摩で出会った足だけ幽霊の渡井季穂まで連れてきた。どうやら季穂は、秋葉原で殺されたらしいのだが、なぜか幽霊として気がついたのが奥多摩だったのだ。東大卒で聡明な権田の力で、最低限のコミュニケーションが取れるようになった警官と幽霊。そこに権田の知り合いの槇村洋六が、交番に駆け込んでくる。大枚をはたいてオークションで落札し、秋葉原のメイドカフェで取引したフィギュアが強奪されたというのだ。さっそく捜査に乗り出した権田と向谷と、彼らに付いていく季穂。やがて彼らは、切ない事件の真相へと到達するのだった。
というのが第一話「オタクの仁義」の粗筋だ。時代小説を中心に活躍している作者だが、現代を舞台にした「神楽坂日記」シリーズもあり、ミステリーの腕前も確かなもの。テンポのよいストーリー展開で、事件の犯人と、きわめてリアルな動機、そしてオタクの仁義による解決まで、一気に読ませてくれるのだ。
その一方、足だけの幽霊の季穂の輪郭が、どんどん彫り込まれていく。秋葉原を嫌っていたり、人間と重なったときその人間の心が読めたりという、後の話で重要な意味を持つ要素が、さりげなく提示されていくのである。そして生前の季穂が、玲那という名前で秋葉原のメイドカフェで働いていたことが明らかになったところで、第二話「メイドたちのララバイ」に続くのだ。
さて、これは私もオタクだから思うのだが、季穂の秋葉原とオタク嫌いは、いささかむかつくものがあった。しかし第二話になって、その理由が、ある種の同族嫌悪から発生するものであると分かり、彼女の見方が変わってくる。徐々に季穂のキャラクターを掘り下げ、イメージを変化させていく小説作法は、さすがというしかない。また、権田たちがかかわる連続メイド抱きつき魔事件の真相も、簡単なトリックで絶大な効果を上げているのである。
以後、三歳児の失踪事件が、親子のハートウォーミング・ファンタジーとなる第三話「ラッキーゴースト」を経て、第四話「金曜日のグリービー」と第五話「泣けない白雪姫」で、いよいよ季穂自身の事件の真実が暴かれる。第四話で彼女を殺した犯人が判明したかと思えば、最終話で、さらに意外な展開になる。幽霊という存在と、その能力を生かしながら、人間の奔走する物語が、いかなる結末を迎えるのか。面白さは保証するので、ぜひとも本を手に取って、確認してもらいたいのである。
ところで本書は、家庭の事情もあって世界を拒否していた季穂が、それを受け入れるまでの物語でもある。作者が巧みなのは、その場所を秋葉原に設定したことだ。とかく奇矯に見えるオタクにも、当たり前の人間の感情がある。その感情が響き合い、共感を得ることで、分かり合うことができるとしているのだ。オタクゆえに、それが際立つ。秋葉原を舞台にした意図は、ここにある。
いや、オタクだけではない。オタクと一般人。生者と死者。さらには幽霊同士まで、分かり合うことができる。現実の厳しさや哀しみを見据えながら、物語全体の読み味は温かだ。他の西條作品と同じく本書にも、人間に対する信頼が、ストーリーの根底に流れているからであろう。
ほそや・まさみつ・書評家
「本の旅人」2015年10月号より転載
※便利な定期購読のお申し込みはコチラ