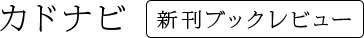「巻を措く能わず」とか「抜群のリーダビリティ」といった、使い古されたフレーズをここで持ち出すのはかなり気が引ける。だが、この『運命の花びら』は、そんな惹句がまず頭に浮かんでしまうような小説なのだ。
今宵こそ吉良上野介の屋敷に討ち込もうという日、浅野遺臣の前原伊助は茶屋で、吉良家奥女中の千尋と同衾していた。吉良の情勢を探るために親しくなったのだが、出会った瞬間からなぜか惹かれてしまい、ついにこの日、結ばれたのだ。そして、明日の朝、一緒に江戸を旅立つことを契り、千尋はいったん吉良邸へ戻ったのだが……。
新選組の山南敬助は、大津の宿で高級遊女の明里を待っていた。新選組を脱退し、共に新しい人生を歩もうとしたのだ。しかし、それを許さない土方歳三は、沖田総司を利用して慰留する。京に戻った山南は、切腹を申し渡されるのだった。そこに駆けつけた明里……。
冒頭の二章が、江戸時代の切ない恋物語が、『運命の花びら』の序曲であり、ベースとなる出会いである。時代は昭和に移り、歴史の一齣となった出来事や、まだ記憶に新しい事件を背景にして物語が重ねられていく。青年将校の反乱、知覧の特攻隊、政治家の金脈問題、大震災、新興宗教の暴走……。
しだいに、遺伝子に組み込まれた運命的な出会いと別れが連鎖していくという、物語全体の構造が明らかになっていく。三百余年にわたる恋物語の連鎖なのだ。そこに気付くと、ますます先の展開に興味が湧く。上下巻、トータルで七百ページを超す大作だけに、ページを繰る手がもどかしいが、登場人物が絡み合っての重層的なストーリーに、すっかり酔いしれてしまう。
そして、今何かと話題の地で長大な物語は収束する。『運命の花びら』の、これまた言い古された表現になってしまうが、感動的でスケールの大きなエンディングにも、圧倒されてしまうのだ。
壮大な構想のもとに書かれたこの長編には、作者の人生が投影されている。生まれ育った埼玉県熊谷市での理不尽な空襲の記憶、学生時代から馴染んだ登山の思い出、サラリーマンの悲哀を痛感したホテルなど、作家デビューまでの歩みをそこかしこに垣間見ることができる。
と同時に、四百冊に迫ろうかという森村作品のエッセンスも、そこかしこでピックアップできるに違いない。ベースは恋愛小説だが、時代小説、戦争小説、青春小説、山岳小説、企業小説、あるいは『人間の剣』のような大河小説と、森村作品の愛読者ならば、いっそう堪能できるはずだ。もちろん、『人間の証明』以下、多くの作品で活躍してきた棟居刑事も登場する。そう、ミステリーの興趣も『運命の花びら』にはたっぷりなのだ。
そして、さまざまな恋物語を彩っているのが詩歌である。立原道造やヘッセ、山岳詩人の尾崎喜八、あるいは作中人物の手によるものと、そこかしこに鏤められている。詩歌もまた一貫して森村作品を特徴づけてきたものだ。そして花びら——。時には季節外れの、時には迷い込んだような一片の、そして時には満開の桜が、登場人物の心情を代弁する。とくにしだいに存在感を増していく桜の花びらからは、日本社会の本質を描こうとする創作意図が窺える。
森村誠一氏の記念すべき最初の著書は、一九六五年に刊行された『サラリーマン悪徳セミナー』である。だから二〇一五年は、作家活動五十周年という大きな節目の年となった。尽きることのない創作意欲にはいつも驚かされるが、とりわけこの『運命の花びら』は、自身の人生と作家活動のすべてを注ぎ込んでいるとしか言いようがない。読み終えたならば、二〇一五年だからこそ世に現れた作品なのだという、至福の余韻に浸ることができる。ただ、作家五十周年はあくまでも通過点である。その余韻のなかで、さらなる話題作を求めてしまうのが、森村作品の読者の性だろう。
やままえゆずる・推理小説研究家
「本の旅人」2015年11月号より転載
※便利な定期購読のお申し込みはコチラ