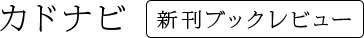近年、ミステリーの世界では「イヤミス」ファンが増えているという。一方、ホラーの世界でも、映像を中心に、相変わらず即物的なスプラッターが人気を集めているようだ。
最近の犯罪報道を見ていると、イヤミス、スプラッターが裸足で逃げ出すようなエグい出来事を目にすることも多い。そういう現実に慣れてしまったために、フィクションの世界でも、現実に負けじとエグさを競い合うようになっているのかもしれない。
でも、そういう時代だからこそ、表面的なおどろおどろしさよりも、人びとの心の奥底に潜む深い闇を探り、人間というものの不思議な性質を見抜く、そういうホラーが必要なのではないだろうか。
辻村深月さんは、この短編小説集の中で、自らの肉声に近いかたちで「こわいもの好き」「無類の怪談好き」であると告白している。だから、こわい描写はいたるところに見られる。でも、直接的な描写としてのスプラッターをはじめ、ぼくたち読者に、生理的なまたは心理的な嫌悪感を催させるような描写は一度も出てこない。
この短編集には、奇しくも十三編が収録されている。辻村さんは、スプラッターやわざと読者の神経を逆なでするような表現に頼ることなく、こわくて奥深い世界を、見事に繰りひろげているのである。その上、作品の長さ(枚数)によって、小説のスタイルを変えているので、多様なこわさを体験できるのが魅力だ。
まず、原稿用紙十枚以下の掌編四編(「丘の上」「殺したもの」「やみあかご」「マルとバツ」)は、無駄のない表現の積み重ねで、クライマックスの場面の映像や感触が、鮮烈に残ってしまう怪談だ。その切れ味の良さは、夏目漱石『夢十夜』、内田百間『冥途』に匹敵する。たとえば、「殺したもの」では主人公が手でつぶしたものの嫌な触感が、ぼくたちにも伝わり、時間とともに生々しさが増してくるではないか。
続いて、十枚以上三十枚未満の五編(「十円参り」「スイッチ」「私の町の占い師」「ナマハゲと私」「タイムリミット」)は、意外なストーリー展開が楽しめるショートショートの傑作である。これらは、星新一や小松左京の名作と並べても遜色のない作品である。なかでも、「ナマハゲと私」は、派手なひねりはないけれど、読後、ゾクゾクと背筋が凍り付くような気持ちになった。
そして、三十枚以上五十枚未満の四編(「手紙の主」「だまだまマーク」「噂地図」「七つのカップ」)になると、単なる恐怖小説ではない。登場人物たちの人生が垣間見えたり、都市伝説など現代の怪談の成り立ちを考えさせられたりする。まさに、ウェルメイドの短編小説を堪能できるのである。
ここに収録された作品群は、ある程度の時間の幅の中で書かれたようで、その間に辻村さんは、妊娠、出産、育児を経験しながら小説を書いていたという。小さないのちに寄り添うというリアルな体験が、これらの作品に新鮮な血を注ぎ込み、上質な短編小説を生み出すことができたのだろう。
ところで、辻村さんのこの短編集に収録された作品の一番の特徴は、書きすぎないことではないかと思う。ホラー小説のような場合、「こわいもの見たさ」ではないが、ついつい恐怖の場面を克明に描きたくなるような気もする。ところが、辻村さんは、登場人物が、そして読者が恐怖に直面する寸前で、さりげなく幕を下ろしてしまう。これが、なかなか効果的なのだ。読後に恐ろしさが、じわじわと迫ってくるのだから。この「寸止め」の鮮やかさに、辻村さんの作家としての成長がはっきりとあらわれている。
『本日は大安なり』『朝が来る』など、見事な語り口に魅了されてきたが、それにこの寸止めの技が加わり、いまや、辻村深月は向かうところ敵なし、とでもいった絶好調の時期にさしかかっている。次の作品も楽しみだ。
まつだてつお・編集者、書評家
「本の旅人」2015年10月号より転載
※便利な定期購読のお申し込みはコチラ