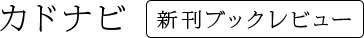そろそろ原田ひ香の認識を改める必要があるのかもしれない。そんな気がしている。
何しろファーストコンタクトが強烈だったので、その第一印象に引っ張られてきてしまったが、もう新しいステージが始まっているのだから、もう少し自由に読みたい。本書を読んで、しみじみとそう思った。
私が最初に読んだ原田ひ香の作品は『母親ウエスタン』で、このインパクトが強烈だったのだ。こんな「ヘンな小説」、それまでに読んだことがない。急いで付け加えるが、私の場合「ヘンな」というのは最高の褒め言葉である。この小説については何度も紹介してきたのでここでは繰り返さない。ぶっ飛びものの傑作である。あわてて遡り、『東京ロンダリング』を読むと、こちらも「ヘンな小説」で、唸ってしまった。私はこういう「ヘンな小説」が大好きなので、すっかりこの作家のファンになったが、いまから思えば、「原田ひ香=ヘンな小説を書く作家」という認識を強固に持ちすぎたと思う。いまそれを反省している。
というのは、たとえば『彼女の家計簿』『ミチルさん、今日も上機嫌』というその後の作品はすべて傑作であるものの、「ヘンな小説を書かせたら天下一品の原田ひ香の小説にそういう展開はありえない」とか、「原田ひ香がそういうストレートな話を書くわけがない」とか、私が書いた新刊評を読み返すと、第一印象に引きずられた感が強いのである。客観的に読めば、『彼女の家計簿』と『ミチルさん、今日も上機嫌』は、展開が新鮮だったり構成に凝っていたりするものの、『母親ウエスタン』や『東京ロンダリング』ほど、「ヘン」ではない。「ヘン」ではないけど、圧倒的に面白い。しかし、「ヘン」というキーワードを持ち続けているかぎり、ではなぜ、すごくヘンな『母親ウエスタン』も『東京ロンダリング』も、そしてそれほどヘンではない『彼女の家計簿』も『ミチルさん、今日も上機嫌』もひとしく面白いのか、という本質が見えてこない。反省するのはその点だ。
「ヘン」というキーワードを外してみると違うことが見えてくる。原田ひ香の作品に共通することが見えてくる。
つまり、愛はいつでも一方通行で、だから私たちの人生はうまくいかないこと。緊張したまま生きていけるほど私たちは強くはなく、どこかに穏やかな時間を持ち、気の許せる友と逢い、ゆったりとした気持ちになることが必要であること。世の中は捨てたものではないこと。人生は一回こっきりのものではあるけれど、しかし一度レールを踏み外してもやり直せること――そういう私たちの人生の真実を、いつも原田ひ香は鋭く、鮮やかに描いてきたのだ。朝は喫茶店、昼はうどん屋、夜はスナックになるという変わった形態の店を舞台にした前作『三人屋』も、そういう道筋で読みたい。飛び道具がなくてもたっぷりと読ませることに驚くのではなく、原田ひ香の小説は最初からそうであったと確認するのである。ようするに原田ひ香の小説は、群を抜くほどうまいから、いつもたっぷりと堪能できるのである。
で、本書ということになるが、これは三人の視点で語られる物語だ。まず、シナリオライター志望の相川健児、その妻の瞳、そして瞳の前夫・一郎太の母親・門脇静江。この三人だ。静江がしょっちゅう電話してくることに瞳はなんだかなあと思っているのだが、健児はテレビを買う相談に乗るだけでなく、一緒に店に買いにまで行く。善良な男なのだ。しかし、なかなか芽の出ない健児の日々。そしてキャリアウーマンとしての瞳の社内での苦労など、それぞれのパートで丁寧に語られるので、徐々に引き込まれていく。
圧巻は、静江が語り手となる章「スカイプ」。その人の不誠実な面を見ないですませることはできる。目を背けていれば幻滅もしない。しかし私は見よう。真実を見よう。たとえ何がどうあっても、まるごと愛することを決めたのだから。その強い思いが行間から立ち上がってくる。
きたがみじろう・文芸評論家
「本の旅人」2015年10月号より転載
※便利な定期購読のお申し込みはコチラ