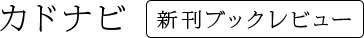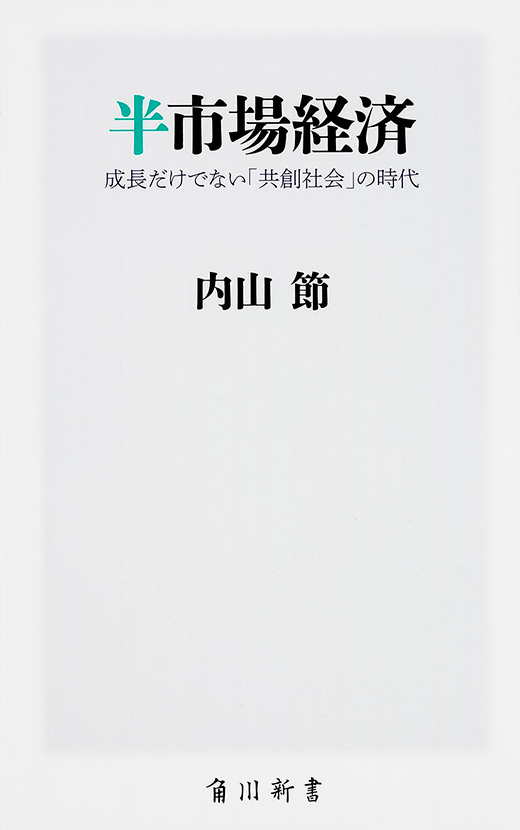この、鋭い問題提起と深い考察に彩られた本について、編著者の内山節は「はじめに」と「最終章」で、誰にでもわかるように簡単に説明している。
まずもっとも重要なのは、本のタイトルにもなっている「半市場経済」という聞き慣れぬことばであろう。それは「市場を活用しているという点では市場経済であるが、活動の目的はよりよき働き方やよりよき社会をつくろうとするところにある。目的は市場経済の原理からはずれている」ものだ。
わたしたちは、「経済活動」といえば「市場経済」しか知らない。いや、ほんとうのところ、説明されれば、他にも経済活動はあるはずなのに、わたしたちが教えられるのは「市場経済」だけだ。そして、その「市場経済」が意味するのは、個人にとっては「いい会社」に入って「多くの賃金を稼ぐ」ための空間である、ということ以外にはないのである。
だが、「経済活動」には、ただ賃金を稼ぐ、もしくは(企業にとっては)利益を生ずる、以外の意味があった。資本主義勃興期の古典的経済学においても「『何のために経済は存在するのか』『人は何を実現しようとして経済活動をしているのか』という市場経済とは異なる思想を、常に内蔵していたのである」。
「何のために」「何を実現しようとして」経済活動をするのか、という、長い間忘れられていた「問い」が、いま甦りつつある。それは、「市場経済」優先の社会が行き詰まりつつあるからだ。そして、その行き詰まりを解消する考え方、やり方こそ、「半市場経済」なのである。
序章の「いま、どんな変化が起こっているのか」では、内山が、「日本の若い世代」が「経済成長が幸せの基礎」ではなく、「現在の」「労働」が「人間たちを幸せから遠ざけていることを知っている」と書いている。おそらく、初めて、「消費の拡大に関心をもたない人々」が増え始めたのだ。このことは、大学の教員として、学生たちと接しているわたしの実感ともよく合う。彼らは、ほとんど「消費」に興味をもたない。そして、この気質は、「消費の拡大」を、その使命とする、現在の社会の「経済活動」の精神と烈しくぶつかるのである。
さらに第一章の「経済とは何だったのか。あるいは、労働の意味を問いなおす」では、まさに、わたしたち現代人の「労働」の意味そのものが問われる。わたしたちの「労働」には「意味」が欠けている。要するに「社会性」が欠けている。それは単に、賃金を獲得するための意味しかないのである。そして、そのことに虚しさを感じることが、新しい労働=新しい経済を生む母体となったのだ。そして、虚しさを感じなくてすむ、「社会性」をもった労働、そのような労働を伴う経済活動こそ「半市場経済」なのである。
第二章の「エシカル・ビジネス」では、「半市場経済」の具体例が示されている。章タイトルの副題に示されているように、その特徴は「『縁』を結ぶ組織」であり「『縁』を結ぶ働き方」ということになるだろう。たとえば、従来の農法が甚大な環境被害を引き起こすことから、「無農薬有機栽培」で、「自然と共存」しながら綿花を育てている農家と共に活動している会社は、その倫理的態度を他の「社会的善」にまで振り向け、様々なCSR(企業の社会的責任)活動を行っている。そのことによって、会社を単なる利益を産む組織ではなく、それに携わることが、生きる意味を産み出すような、新しい形の共同体としたのである。
本書の全体を通し、内山を筆頭とする執筆者たちは、現在の経済活動とその本質を異にする、様々な新しい労働、新しい経済活動を紹介している。わたしたちは、そんな、新しい、社会性をもった経済活動を、「言っていることは正しいかもしれないが、現実には……」と目を背けてきた。本書が主張するのは、まさに、このような「半市場経済」の現実性だろう。それは、いつでも始めることができる。わたしたちに、勇気がありさえすれば。
たかはしげんいちろう・作家、明治学院大学国際学部教授
「本の旅人」2015年10月号より転載
※便利な定期購読のお申し込みはコチラ