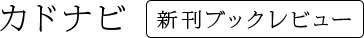学校新聞を見て、驚いたことを思い出す。私が中学3年生のときだ。そのときの学校新聞には、「図書館から借りた冊数の多い生徒のベスト10」が載っていた。ようするに、学校の図書館から1年間に何冊借りたか、というランキングである。私が驚いたのは、そのとき1位になった生徒(当時の生徒会長だ)の借りた冊数だ。なんと200冊を超えていた。230冊か240冊か、細かな冊数は忘れてしまったが、とにかく200冊超え。1年間にそれだけの本を読む中学生がいるとは、まったく信じられない。
この話は以前もどこかに書いた記憶があるのだが、いきがかり上続ける。そのとき私はその生徒会長を「なんと可哀相な奴」と思ったのである。1年間にそれだけの本を読むということは、その間ほかに何もしないということだ。本を読むことに時間が取られるのだから、そうなるのも仕方がない。つまり彼は、野球の楽しさも知らなければ、映画の楽しさも知らないに違いない。中学生の私はそう考えたのであった。
当時の私たちは少年野球に夢中だった。いまのリトルリーグとは違って、少年野球というのがあったのである。各警察署の少年課が主催(後援だったかも)していたところをみると、非行防止という目的があったのかもしれない。大人の監督やコーチがいなくても子供たちが勝手に申し込めば誰でも出場できるのが魅力で、私は毎年目白警察の少年課に出場申し込み書を提出しに行った。のちのリトルリーグほど本格的ではなく、部活とちがって先輩も不在、ようするに少年たちの草野球である。中学3年間はその練習に明け暮れるか、映画を観にいくか(当時は第何次かの西部劇ブームだった)、そのどちらかで過ぎていった。本など読んでいる暇はないのだ。
つまり私は中学を卒業するまで一冊の本も読んだことがない。あることをきっかけに小説の楽しさを知り、それ以降深入りすることになるのだが、それは別の話である。問題はではなぜ、一冊の本も読まなかったのかということだ。それは教科書に載る「蜘蛛の糸」とか「清兵衛と瓢箪」などの小説がつまらなかったからだ。小説というのは、そういう「退屈なもの」であり、押しつけがましい教訓の代名詞でもあった。そんなものを読んでいる時間があったら、球をおいかけていたほうが遥かに楽しい。
しかし、もしあのころ、本書のような小説を読んでいたら、おそらく違っていたのではないか。そんな気がしてならない。本書『ママは12歳』は、1977年に刊行された『ちびっ子かあちゃん』を改題したもので、40年近く前に書かれた小説である。ところがどうだろう。いま読んでも面白いのだ。
この物語の主人公田口らん子12歳は、母親が病気で亡くなってしまったので、小学3年生の研作と1年生の大作、二人の弟の面倒を見ている。食事を作らなければならないし、掃除洗濯もしなければならない。目のまわるような忙しさである。さらに、亡くなった母親の妹である山井はま子が、露骨にらん子たちの母親になろうとしているから油断できない。このおばさんは、母親が病気のときはまるでそばに近づかなかったくせに、母親が死んだらしょっちゅう田口家に出入りするようになったのである。人のいい父親はよろしくお願いしますと言ってしまうが、食事を作るどころか店屋物を注文するだけ。時には出前を取りもしないのに代金を父親に請求したりする。だから、らん子は断固反対。
そういうらん子の奮闘の日々が活写されるから楽しい。イヤなやつは最後までイヤなやつだったという結構がなによりもいいし、あの「教訓」は微塵も出てこない。らん子は自由奔放な女の子だが、物語もひたすら自由で、のびのびしている。少年のころの自分に、この小説を届けたい。そんな気がするのである。
きたがみじろう・文芸評論家
「本の旅人」2015年10月号より転載
※便利な定期購読のお申し込みはコチラ