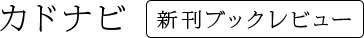一番身近な他人、それは医療関係者である。生まれて最初に出会うのは親ではないし、亡くなる寸前に脈を取ってくれるのはお医者さんである確率が高い。いくら頑健であることを自慢していても、ひとたびどこか具合が悪くなれば頼るのは治療してくれる人。人生で常に関わってくれる仕事が医療である。
昔から小説の世界でも医療を取り上げた作品は多いが、この十年ほどは「医療小説」というジャンルが確立された。病気を治すことだけではなく、行政や歴史、経済に至るまで医療に関わる小説は増えている。
医師として仕事を続けながら小説を書く作家も増えている。その中で、久坂部羊はここ最近「キテいる」作家だと思う。二〇一四年、『悪医』(朝日新聞出版)で第三回日本医療小説大賞(日本医師会主催)を受賞し、その後も続々と新刊が上梓されている。その上、この十月から『破裂』と『無痛~診える眼~』の二作がドラマ化され話題となっている。
二〇一五年初の小説となる『虚栄』は、これぞ医療小説! という作品となった。大学病院を舞台に政治的駆け引きや名誉の奪い合い、医師としての優越感も劣等感も矜持も倫理観もすべてを備えた重厚な作品である。
二〇一×年、歌舞伎俳優やタレント、歌手などの著名人が立て続けにがんで亡くなった。かれらはみな、健康診断を毎年受けていたにもかかわらず、診断から死亡まで数ヶ月という早さで進行しており、特別ながんであるとマスコミは騒ぎ立てた。日本のがんは凶悪化したのか? その問いに専門家はこう答えた。
「日本の医療は世界最高のレベルです。がんの凶悪化の原因は、いずれ解明されるでしょう。そして必ずや、新しい治療法も開発されるに違いありません……」
引き込まれずにはいられないプロローグである。秋から冬になると毎年話題になる新型インフルエンザや、この春、韓国で大きな問題となったMERS(中東呼吸器症候群)など、未知の病気の恐怖は誰にとっても身近な問題だ。
ましてや、日本人の二人に一人はがんになると言われる現在、最も身近で恐ろしい病ががんである。実際、がんに罹った身内や友人がひとりもいない、という人の方が珍しいだろう。それだけにこの凶悪化は現実的だ。
忌まわしい凶悪がんの対策のため、政府は「プロジェクトG4」という重要政策会議を立ち上げる。外科、内科、放射線科、免疫療法科の四方向からのアプローチをそれぞれ得意とする大学に振り分け、研究を競わせたのち、力を統合して総力戦によってこの病の克服を目指すという。
手術で患部を切り取ってしまうのが一番という阪都大学、抗がん剤治療を得意とする東帝大学、放射線によって患部を粛清することで患者の負担を減らすという京御大学、副作用のない新しい治療法である免疫療法をアメリカから導入した慶陵大学。研究者たちはほかの大学より一歩でも先んじようと新しい研究に没頭する。
しかし正攻法だけでは成功は手に入らない。政治家にすり寄る。機械メーカーや製薬会社と密約を結ぶ。時にはマスコミにスキャンダルをリークして大バッシングを繰り広げていく。医療小説の金字塔とも言われる山崎豊子『白い巨塔』の時代よりさらに非情になった医局のヒエラルキー。過激で残酷な権謀術数が繰り広げられていく。
成功する者もあれば転落していく者もいる。ひとつひとつのエピソードはここ数年で明らかになった医療や科学関係の事故やねつ造などを彷彿とさせ、一般の人には見えてこない裏の駆け引きに「そうだったのか」と驚かされる。小説だとわかっていても戦慄を覚えるほどリアルだ。
人の命を救うこと、それを目指して医者という職業を選んだはずだ。その意志を最後まで貫き通すことが出来るのか。がんという病気は果たしてなぜ存在するのか。大きな命題を私たちに突きつけてくる物語であった。
あづま・えりか・書評家
「本の旅人」2015年10月号より転載
※便利な定期購読のお申し込みはコチラ