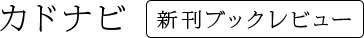夕暮れ時に公園の緑色のベンチに座って待っていると記憶屋が現れて、忘れてしまいたい記憶を消し去ってくれるらしい——第22回日本ホラー小説大賞読者賞を受賞した織守きょうやさんの『記憶屋』は、そんな都市伝説をめぐる物語。非常に味わい深い群像劇になっている。
吉森遼一が記憶屋を知ったのは、幼い頃に近所の老人たちが噂していたからだ。大学生になった今、彼は実際に記憶を消されたらしき人物を知っている。一人は年下の幼馴染み、真希。子供の頃、ある出来事が起きて大泣きした翌日、彼女は泣いたことすら覚えていなかった。もう一人は、思いを寄せた女性だ。大学に入学してほどなく飲み会で知り合った一学年上の澤田杏子は、痴漢に襲われたことがトラウマで、夜道を一人で歩けないという。遼一が家まで送るといっても、彼自身のことも怖く思えてしまう、というのだ。ようやく彼女が彼に心を許してきたと思えた矢先、杏子は人が変わってしまう。痴漢にあった記憶がなくなり、夜道を怖がりもしない。それどころか、遼一との交流も忘れてしまっていた。彼の頭に浮かんだのはもちろん、記憶屋の存在だ。さらにある時、彼は愕然とする。記憶屋について調べようとしていた過去を、すっかり忘れている自分に気づいたのだ。記憶屋は実在すると確信した彼は、ネットを駆使して本格的に情報を集め始める。
次のエピソードでは遼一の大学に講演に来た弁護士、高原の物語へと移行していく。彼の世話をする青年の目を通して進行していくのは、普段は軽いノリだがある秘密を抱える高原と、彼になついている女子高生との交流だ。その次に描かれるのは、中学生の少年と少女の気持ちのすれ違い。彼らに起きる出来事には、なんらかの形で記憶屋が絡んでいる。そして最終章は再び遼一の視点に戻り、意外な真実が明かされていく。
ホラー小説大賞入選作とはいっても、いたずらに読者の恐怖心を煽るような内容ではない。ただ、もしも大切な記憶を消されてしまったら、と考えるとゾワリとするものがある。というのも、本書に並ぶエピソードはどれも、記憶を失った人たちが、同時に大切な何かを失ったと思えてしまうのだ。誰も悪意など持っていない。むしろ彼らは大切な誰かのために、自分の、あるいは他人の記憶を消そうとしただけだ。しかし、それははたして、善き行いだと言えるのか。たとえば遼一が思いを寄せた杏子はトラウマから解放されたものの、成就しそうだった恋を台無しにしてしまったのだ。すべてを憶えている遼一にとってこんなに辛いことはないだろう。だからこそ、彼は記憶屋に固執するのだ。
その人にとって忘れられない記憶を消し去ることは、その人の人格形成にまで影響してしまう。それは好ましい結果を招くとは限らない。終盤、ある人物に向かって遼一は言う。
「記憶をなくすってことは、後悔するチャンスさえ与えられないってことだろ?」
後悔というマイナスの感情でも、人には必要なのだ。ファンタスティックな設定のなかで、人生と記憶という根源的な題材と真摯に向き合い、人にとって大切なものは何かを問いかけてくる。そこが、本書全体を包む切なく優しい空気を作りだしている理由だ。
文章も柔らかく読みやすく、物語を語りなれている印象。それもそのはず、著者の織守氏は第14回講談社BOX新人賞Powersを受賞し、青春ホラー『霊感検定』で、すでに2013年にデビューを果たしている。現在は弁護士として働く傍ら小説を執筆しているという(本書に弁護士が出てくるのも、自分に身近なものとして書きやすかったからだろうか)。着眼点からの話の広げ方、落としどころ、人物像の作り方などに安定感があるこの著者。切なさのまじった瑞々しいホラーの書き手として要注目の、1980年生まれの若手である。
たきいあさよ・ライター
「本の旅人」2015年11月号より転載
※便利な定期購読のお申し込みはコチラ