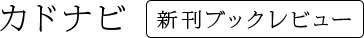著者の室井尚さんと私はほぼ同時期(1990年代はじめ)に大学教員となり、それから四半世紀を大学教育の現場で過ごしてきた(私は2011年に神戸女学院大学を早期退職したが、そのあとも別の大学に理事や客員教授としてかかわっている)。私が勤めていたのは私立のミッションスクールであり、室井さんは国立大学なので、大学の雰囲気や運営ルールはずいぶん違うはずだけれども、四半世紀の間に経験した環境の変化はおおすじでは同じものだと思う。それはこの本の中でも繰り返し指摘されている通り、まったく無意味な仕事の増大によって教員たちの研究・教育の時間とエネルギーが壊滅的に損なわれたということである。
ある時期から大学には「まったく無意味」としか思えない制度変更の通達や規則が文部科学省から雨あられのごとく下りてくるようになった。それについて「何を根拠に文科省はそのような制度変更が有用であると判断したのか」「その制度変更の適否の検証はいつ、どのようになされるのか」「その制度変更が失敗だった場合、誰がどう責任を取るのか」というたぐいの(少しでも知性がある人間なら誰でも思いつくはずの)問いはすべて封殺された。いいから黙って言われる通りにしろ。言われる通りにしなければ助成金や運営交付金をカットすると上から一方的に告知された。
室井さんはそれを「手続き型合理性」と命名している。研究倫理やセクハラやエアコンフィルターの掃除確認に至るまで「手続きだけをきちんとするために膨大な作業があらゆるところで発生している」のである。「膨大」というのは誇張ではない。今では大学教員は、そのような日々送られてくる何の意味もないが空欄を満たさなければならない書類書きのために疲れ果てている。
私の個人的経験を話す。教務部長をしているときに「シラバスをもっと詳細に書け」という通達が来た。私は自己評価活動についての長年のアンケート調査によって、シラバスの精粗と学生の授業満足度の間には何の相関もないという統計的結論を得ていた。学生がろくに読みもしないシラバスに、一年分の授業予定や期待される教育効果などを細密に書き込むのはただの徒労である。私は骨の髄まで合理主義者なので、このような無意味な労役に耐えることができない。だから、通達を無視した。翌年、助成金がカットされた。私はこの処分に怒りを抑えることができなかった。
ここには二種類の退廃が見て取れる。一つは「上が決めたことについて適否の判断をする権利は大学人にはない」という考え方である。権力を持つものはそれが下す指示について、その合理性や根拠を国民に開示する義務を免ぜられていると彼らは信じている。私はこれを名づけるのに「反知性主義」以外の呼称を思いつかない。もう一つの退廃は処罰がほとんどつねに「金」の分配によってなされていることである。不服を申し立てる大学人を呼び出して、政府の政策の正しさを情理を尽くして語って納得させるというような手間ひまを教育官僚は取らない。「ああ、そうですか。じゃあ、お金をあげません」で終わりである。ここには「人間は金で動く」という彼らの個人的信念がはしなくも露呈している。「上に無批判に従う人間」「金で動く人間」「ことの理非の判断に際して自分の知性を使わない人間」を組織的に生産すること、それがわが国の教育行政の最優先の政策課題なのである。ほんとうに恐ろしいことだと思う。
日本の大学教育はこのまま終わるのか、それとも再生のチャンスはあるのか。それについては室井さんが学生たちの潜在的可能性の豊かさと私塾の発生を手がかりに一握りの希望を語っている。私自身もこの希望にあるだけの賭け金を置く他ないと思う。
大学の現状を活写し、希望について語るということを限られた紙数のうちに果たした室井さんの努力に一人の大学人として感謝したい。
うちだ・たつる 神戸女学院大学名誉教授
「本の旅人」2016年1月号より転載
※便利な定期購読のお申し込みはコチラ