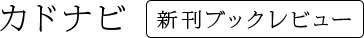この本には、平安末期から鎌倉時代を生きた、おもしろい人物がおおぜい登場する。読むほうは、あまりかたくるしいことを考えずに、彼ら彼女らのことをたのしめばよい。
なじみのない人名も、けっこうでてくるが、それらもてぎわよく解説されている。歴史が好きだという読者には、安心してすすめられる本である。
ただ、登場人物の人となりがきわだつのは、たくみな叙述のせいだけでもない。時代そのものが、型破りな人間の出現をうながした。平安のおわりごろから、時代はいやおうなく、そういう方向へうごいていったのだという。
いわゆる院政期には、朝廷の箍がゆるみだした。摂関期までの秩序が、くずれだす。そんな時勢のなかで、宮廷をとりまく社会も、様変わりを余儀なくされるようになる。史上のあやしい、またとんでもない人々に光をあてつつ、著者はそこをえがきだす。これは、院政期以後の社会変容を、人物群像のなかで浮き彫りにしようとする本でもある。
かつての古典的な歴史研究は、武士の台頭にこそ、新時代の到来を読みとろうとした。京都の王朝については、とりのこされた古い世界として、位置づけたがったものである。とりわけ、東京大学を中心とする関東の歴史家に、その傾向は強かった。
だが、著者は、朝廷をとりまく社会も、大きく変容をとげていると見る。中世的発展を、混沌というべきかもしれないが、京都にもみとめている。関東の歴史家も、ずいぶん畿内へあゆみよりだしたものだなと、感じいる。
話題は、宗教がらみのものが多い。といっても、仏教の教理教典などは、ほぼおきざりにされている。語られるのは、そういう御本尊めいたテーマでなく、寺院経営の雑務などである。いくつかの寺や僧侶は、資本主義の 先駆者めいた存在として、あつかわれる。
建築史に興味のある私は、なかでも勧進と法勝寺の問題にひきつけられた。
法勝寺は、白河院政がつくりだした巨刹である。高さが八十メートルにもおよぶ九重塔さえ、そこにはたてられた。院権力が、これ見よがしの自己顕示にはしったのだと、みなしうる。
建築史家の山岸常人は、この法勝寺に専属の寺僧がいなかったことを、強調する。そして、それが宗教抜きのモニュメントにかぎりなく近いことを、力説した。いっぽう、中世史家の上島享は、この説に批判的な立場をとる。法勝寺の近くには僧侶がいたし、寺内にも法要をいとなむ施設はあったという。
この上島説をとれば、院政期の新寺院も摂関期のそれらと、質的にはかわらなくなる。変化があったとしても、それは量的な肥大化でしかないことになってしまう。山岸説のほうが、院政期からの変革を論じる著者にとって、都合はいい。
そのせいかどうか、著者の書きっぷりも、やや山岸説に好意的である。異形を生みだす院政という話になじみやすい山岸説へ、よりそっている。とはいえ、それなりに論拠もある上島説を、あからさまにしりぞけたりはしていない。山岸説へは、けっこう用心深くあゆみよっている。
じつは、私も山岸説に魅力を感じるひとりである。だが、ある一点でわだかまりもいだいてきた。
日本の寺には、飛鳥時代以来、見てくれの都合で造営された面が、多分にある。鑑真は修行の道場さえあればじゅうぶんで、伽藍などいらないと言いきった。その価値観に立脚すれば、寺院史をいろどる名刹は、みなモニュメントになってしまう。寺院以外のモニュメントがあらわれだす室町後期までは、連続的にとらえうることとなる。
飛鳥以後、室町前期までを、ひとつづきの時代として見てしまう。摂関期と院政期のちがいがかすんでしまうこういう見方を、著者はどう思うのか。いちど、お話をうかがいたいところである。
いのうえ・しょういち 国際日本文化研究センター教授
「本の旅人」2016年1月号より転載
※便利な定期購読のお申し込みはコチラ