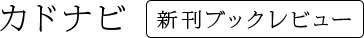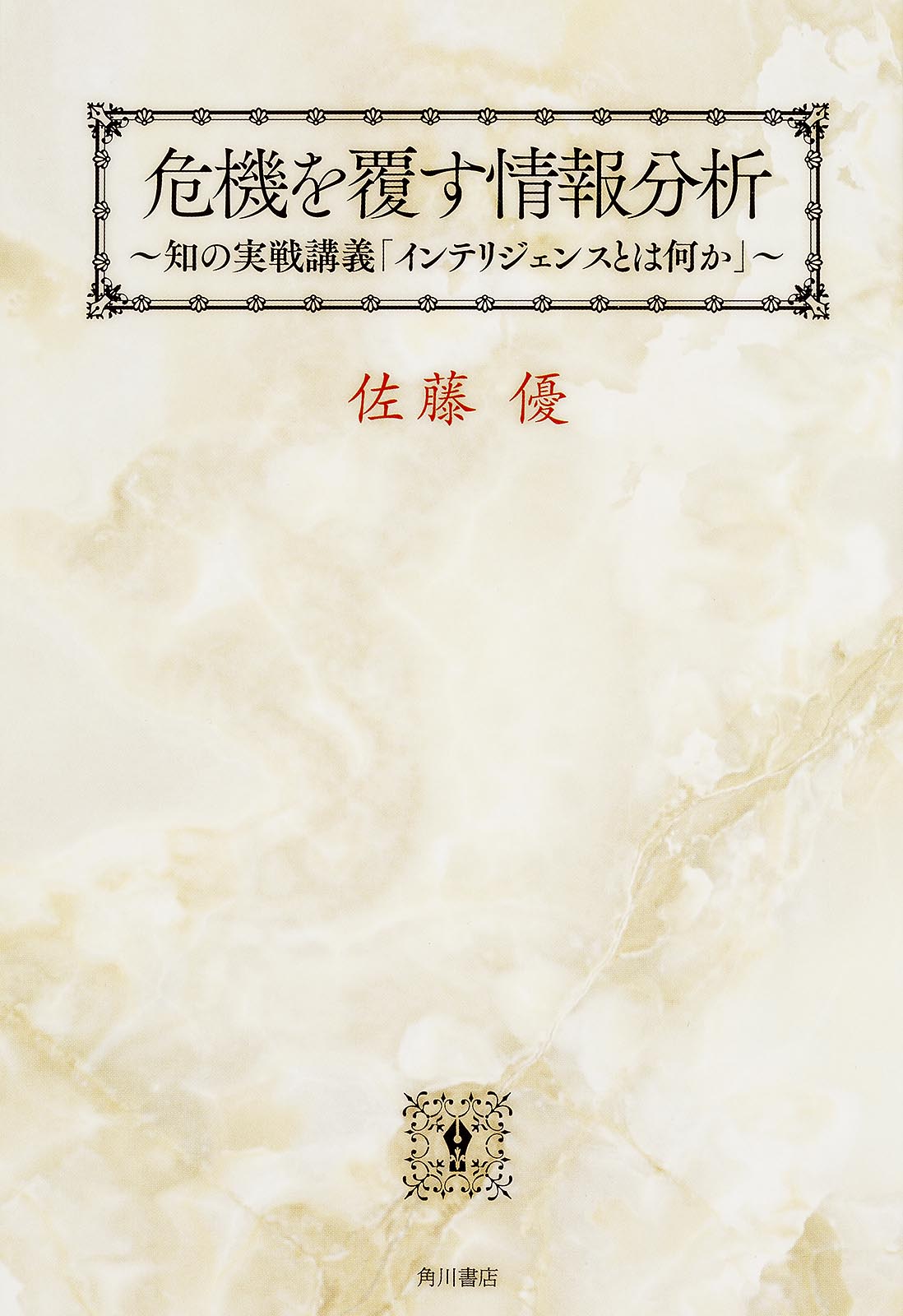今年の年頭記者会見で安倍晋三首相は「挑戦」という言葉を24回連呼した。早々に召集された通常国会について「未来へ挑戦する国会だ」とし、一億総活躍社会については「いかに困難な挑戦であったとしても、一億総活躍の苗木を植える挑戦をスタートしたい」(東京新聞・1月5日付朝刊)と述べている。昨年、安倍首相の語彙力の欠如を突く記事へのコメント依頼を何度か受けたが、欠けているのか、それとも巧妙に策定されているのか、即断するのは難しい。ワンフレーズで大多数を釣り上げた小泉純一郎の話法に準じるようでいて、少々異なる、似通ったフレーズを節々に染み込ませて煙に巻くような彼の話法は、功を奏し続けている。「未来へ挑戦する」もそのひとつだが、これは「現実と対峙する」の対義語でもある。永久的に用意される未来に挑戦し続けることは、もっとも安全な航海と言える。
佐藤優は「悲観論者とは、情報に通暁した楽観論者のことをいう」という俚諺を引っぱり、「危機を覆す情報分析を身に付けると、確かに世の中が少し暗く見えるようになるかもしれない。しかし、暗さは暗いと認識して初めて、明るくするための現実的方策を考えることができるようになる」と記す。ここに「灯台下暗し」という手垢まみれの諺をぶつけてみると、「未来へ挑戦する」政治の危うさが見えてくる。灯光のように遠くを照らし続けることで、足元に広がる暗部の識別を怠る。例えば「イスラム国」(IS)に日本人の人質が拘束されても、そして殺められても、「テロに屈しない」でやり過ごそうとした政治手法など、その灯光の一例。行く先の指針ばかり連呼し、直面した危機に対し人目をたぶらかした。
本書は2013年から14年にかけて行われた講義を、「情報」「スパイ」「勉強」「教養」の4項目としてまとめた一冊だが、佐藤が始終繰り返し訴えてきたインテリジェンスをいよいよ個々人が実践モードに移さなければ危うい時代に入ってしまったのだろう。講義で「インテリジェンスは基本的に国家の仕事」と語っていた佐藤は、講義を終えた後の「あとがき」で、本書を通じて訴えた知性が「現下日本の政治エリートの中では根付いていない」ことを問題視する。
その上で「危機を克服する知性を是非とも政治家に身に付けて欲しい」と締めくくるのだが、「挑戦」を24回連呼する政治家たちにそれを望むことはもはや不可能だろう。かといって、私たちがその注視を緩めると、行き先を照らし続けるだけの「灯台政治」を許容したと見なされてしまう。それこそインテリジェンスに欠ける国家の在り方ではないか。
このところ、新世代の広告マンや編集者などの持論が詰まったビジネス本を開くと、感情をシェアする、背景にあるストーリーに共感してもらうというメソッドが必ずや顔を出す。エンターテインメントの世界と国家や政治のフィールドは明らかに異なるのだが、佐藤が今は「物語が欲しい」時代だと指摘するように、誰かが策定したストーリーに民意が安直に流されやすくなっている。「反知性主義」という言葉は誤読も含めて流行したが、その事象は、知性を回避したほうが感情に訴えかけやすい、という手法が招き出したもの。つまり、知性を薄めて物語を盛って投与するほうが、あいつらには届きやすいと思われているのである。
本書では、その手の環境に屈しないための思考と実利を得るためのアイディアがいくつも投じられるが、軸となるのは「類比的な思考を身に付けるために不可欠な」ジャンルである「歴史」。前を向いて物事を直視した結果として悲観に至ることはちっとも後ろ向きなことではないはずだが、感情やストーリーが先立つ社会では、悲観してちゃいけないよ、と体の向きを勝手に変えられてしまう。これって、思想的に左だ右だの議論の前に、抗わねばならない部分ではないか。そのためには歴史を学ぶべし。本書には、自分の向きを当たり前に保ち続けるための助けが詰め込まれている。
たけだ・さてつ フリーライター
「本の旅人」2016年2月号より転載
※便利な定期購読のお申し込みはコチラ