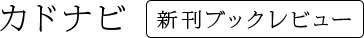母がまだ幼い妹とわたしに向かってこう言ったことがあった。
「あのな、お母さんが死んだら、二人に半分ずつ保険金が入るようにしてあるからな」
だから安心するように、と母は言いたかったのかもしれない。わたしと妹は母がいなくなることを想像し、それぞれに絶望して泣いたり、どう理解してよいかわからず硬直したりした。
本書には植物状態になった父と二人の息子が登場する。不慮の事故に巻き込まれた父の延命治療をするべきか否かの状態にある。
延命治療しなければ父は死に、兄弟には自動的に二億円が入ってくる。その事実を前に兄弟は別々の答えを出した。
兄・一也は仕事が長続きせず、これまでも困ると父に泣きついて助けてもらった。そして今も新しい事業を始めるために金を欲している。病を抱える息子のために金はいくらあってもいい。有り体に言えば父の命より金である。
一方、腎臓病だった弟・次也は、父から腎臓の移植を受けて救われた過去がある。しかし年月を経て、腎臓廃絶の不安を抱えていた。父を自分の守護神と信じ、父が生きてさえいれば自分も大丈夫だと思っている。金よりも父の命だった。
子どもの頃から兄に翻弄されてきた次也は、父の命かお金かの選択で、次第に心が揺らぎはじめる。本書は次也の視点で進められるゆえに、読み手は次也同様に動揺してしまうだろう。
それは物語に入り込んでしまうからだけではなく、こういうことは誰にも起こりうることだからだ。たとえば次也と同じく家族の延命治療をするか否か、という選択を迷わずにいられるか、迷った上に決断して、後悔しないと言い切れるか。はっきりとした正解はないし、間違いもないから、どの道を選んでもきっと苦しい。
本書のみそは、父が死ぬと高額の相続金が発生するところだ。たとえば気まぐれに宝くじを買っただけでも「一等が当たったら家を買って、海外旅行をして……」と想像を膨らませたりするが、次也もまた父の延命を止めれば転がり込む二億円(兄弟で分けて一億ずつ)の数字が差し出されて、その使い道を想像しないではいられなかった。
そういう次也の弱さは自分の中にもあるものだ。同時に父を延命させることは果たして誰のためなのか、と考える。自分のためか、父のためか? 生きるとはただ呼吸するだけではない。長年の透析生活で食事や運動などを制限されてきた次也だからこそ「生きる」とはどういうことかが切実に迫ってくる。もちろん植物状態の父には確かめられない。周囲が決めるしかないのだ。
こうして心を引き裂かれ、ぼろぼろになりながらも次也は一つの決断をする。その決断は大きなうねりとなって彼を巻き込んでいき、思いがけない登場人物が事態を一転させるが……続きは是非読んで確かめて欲しい。
次也の弱さや実直さは愛おしいし共感するが、本音がどこにあるかわからない一也の造型が悪い奴だとわかっていても何とも魅力的だ。一也の妻・玲子の何を考えているかわからない怖さにも震えた。玲子の大胆不敵な行動は大金を前にした人の欲望がなせることか、いやただ病気の子どもを救いたい母の姿か、答えは明かされない。
人間がいざという時、どんな顔を見せるかを小説の中であらわにし、綴られる文字を鏡に読み手は自分の顔を発見する。読書中とにかく翻弄され、自分の弱さを思い知り、ラストでは心救われた。ありがとう、周防さん。なんとか生きていけそうです。
読み終えて、かつて硬直したあの日を思い出し、ふと気づいた。
「そういえばお母さんの保険金、いくらだったか聞いていなかったな」
なかえ・ゆり 女優、作家
「本の旅人」2016年3月号より転載
※便利な定期購読のお申し込みはコチラ