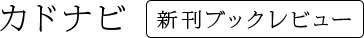もう驚かない。新野剛志が『あぽやん』を書いたときには、「あの新野剛志がこういう軽妙な小説を書くのか」と驚いたものだが、その『あぽやん』で大きく変わった作家であるから、本書のような軽妙路線の傑作を書いても、もう驚かない。
本書の主人公は、星野親27歳。私立の保育園みつばち園で働き始めるところから幕が開く。本当は公立の保育園に勤めたかったのだが、公務員の試験に落ち、1年だけの契約社員としてみつばち園で働くことにしたのだ。みつばち園で働く保育士仲間の辻あかり、酒井景子は「1年だけですって。うちはただの、繋ぎということですよ。そういうつもりで就職することをなんて呼ぶんでしたっけ」「腰掛けでしょ」と口うるさいが、井鳩園長は「うちの園、始まって以来の男性保育士さんだから、すごーく期待しています」と優しい。というわけで、星野親の保育士生活がスタートすることになるが、同じ市内の保育園に勤務する男性保育士の会に出席して、みつばち園が勤務先であることを告げると、「そうか、それじゃあ大変だな。ダイナマイト・ハニーに勤めてるんじゃ」と言われてびっくり。なんですか、そのダイナマイト・ハニーって?
それは本書を読んでいただくとして、とにかく次々と問題が起こるから目が離せない。園長を始め、働いているのは星野親27歳以外は全員女性だから、それだけで着替えはどこでするとか、細かな問題がある。母親たちの飲み会に誘われ、あまり飲めない星野親は泥酔してわけがわからなくなったりするし、クレームをつけてくる保護者もいるからそのたびに彼は振り回される。さらに現代の縮図ともいうべき光景が保育園にはある。たとえば本書でいちばん強い印象を与える光景は、酒井景子が園児を後ろから抱きかかえ、匂いを嗅ぐ姿だ。最初星野はその姿を微笑ましいと思うのだが、やがてその酒井景子の行為には違う意味があることに気づく。そのくだりを引く。
「うちの園には虐待やネグレクトのおそれがある子供が何人か通っていた。みつばち園ならなんとかうまくやってくれるだろうと、市から回されてきた子たちだ」
だから、ちゃんと風呂に入れてもらっているかをチェックするために頭の匂いを嗅ぐのだという。着替えのときには怪我はないか、痩せてきていないかをチェックする。酒井景子が園児を後ろから抱きかかえる姿の向こうにあるのは、そういう厳しい現実である。こういう例がさりげなく、この小説のあちこちに描かれている。さらに、どうにも解決できないことだってある。保育園には限界もあるのだ。そういうリアルな現実をも本書はきっちりと描いているので時には哀しくなったりする。
もちろん、『あぽやん』と同様に、個性的な登場人物が出てきて、軽妙なやりとりがあることも書いておかなければならない。きつい目をして、いつも不機嫌そうな景子先生を元ヤンキーじゃないかと星野は疑っているが、その景子先生の事情はずいぶんあとになって語られる。星野が保育士をめざした動機も語られるが、この挿話もなかなかいい。ストーリーはネタばらしになるのでなるべく紹介しないほうがいいのだが、早い段階に出てくる回想なのでこれくらいはいいだろう。中学3年のとき父親の転勤で見知らぬ土地に引っ越し、友達も出来ずに不安と孤独に押しつぶされそうになっていた夏休み、幼いころに通っていた保育園に彼は行くのだ。夏休みに行くところがないなら遊びにおいで、とかもしか保育園の園長が言ってくれたので毎日通い、園児たちと遊ぶことで彼は立ち直っていく。とてもいい挿話だが、この回想があるから物語の後半に「夏の終わりにやってくる子はね、だいたい心に何かを抱えてるものなの」というみつばち園の園長の言葉が胸に染みてくる。うまいなあ、新野剛志は。
きたがみ・じろう 文芸評論家
「本の旅人」2016年4月号より転載
※便利な定期購読のお申し込みはコチラ