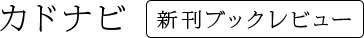四十にして惑わず――と『論語』にはあるが、実際その歳になってみると、〝不惑〟というにはほど遠い、惑うばかりの自分がいて苦笑するしかない。しかし、安藤祐介『不惑のスクラム』を読むと、〝不惑〟を気取ってなんでもわかっているようなふりをするくらいなら、不安や焦りを抱えても惑うことから逃げない愚直な生き方のほうが人間らしいではないかと思えてくる。それも、熱い涙をはらはらと流しながら。
物語は、死に場所を探して半日近くも歩き続けた丸川良平が、江戸川河川敷に行き着くところから始まる。
最後の金で手に入れた錠剤を飲み下し、目の前に広がるすすきの原に寝転んで43年の人生に幕を下ろそう。そう考えていた丸川だったが、そこに、近くで練習していたラグビーチームのボールが不規則にバウンドしながら転がってくる。拾い上げた丸川が、グラウンドに向けて力任せに蹴り飛ばすと、ラガーマンたちからどよめきが起こった。じつは高校時代、丸川はスピードと当たりの強さに加えキックの能力が求められるディフェンスの要――フルバックとして活躍したこともあるラグビー経験者だったのだ。
別の死に場所を探さなくてはと、すぐに立ち去ろうとする丸川に、細身の老ラガーマンが、人生を大きく変える言葉を投げ掛ける。
「一緒にラグビーやりませんか」
こうして、丸川を呼び止めた老ラガーマン――〝ウタさん〟こと宇多津貞夫が23年前に創設した40歳以上のシニアラグビーチーム――大江戸ヤンチャーズに加入することになった丸川が、一度は背を向けたラグビーにふたたび目覚め、失っていた自分の居場所と生きる活力をどう取り戻していくか――というストーリーが動き出すのだが、本作をただシニアラグビーを題材にしたスポーツ小説、あるいはドロップアウトした中年の再生物語と考えるのは早計だ。そうした要素は、確かに含まれてはいる。しかし、その括り方では伝え切ることのできない滋味深い様々な魅力が、この小説にはたっぷりと詰まっているのだ。
なぜか決して電車に乗ろうとしない丸川が、どうしてラグビーをやめ、家族と別れ、自ら命を絶とうとするまでに至ったのか。その謎が次第に明かされるとともに、チームメイトたちそれぞれの職業や抱えている事情、内に秘めた想いにも順にスポットが当てられ、そうしたエピソードの数々が、じつに強く深く、読んでいるこちらの社会人としての心に響いてくる。ある者は仕事でモンスター部下の扱いに苦心し、私生活では男手ひとつで育ててきたひとり娘が抱く親への想いに改めて気づき、ある者は会社でのくだらない陰口を聞き流しつつ、ヤンチャーズの運営と突如持ち上がった丸川絡みの深刻な問題に頭を悩ませ、そしてある者は仲間たちに向けた最後のメッセージを遺そうとし、別のある者は……といった具合に、会社員小説、家族小説、老年小説などの要素も巧みに織り交ぜながら、重い過去を背負った丸川の変化だけでなく、丸川の加入によってチームメイトたちの人生にも新たな変化が訪れる様子を温かく描き出していく。
惑うことは無様であるかもしれない。しかし、不惑を過ぎてなおひたむきに惑い続けながら、「グラウンドで会おう」の言葉を胸に集まり、無心に楕円のボールを追い掛ける――まさに〝不惑のスクラム〟というべき固いつながりのなんと輝かしいことか。
ここまででも十二分に目頭が熱くなってしまうが、これで終わりではない。
クライマックスで、丸川は試合の終盤にあることを試みる。その想いを皆が一瞬で理解し、祈るような気持ちを抱く場面は、万感胸に迫る名シーンだ。これまでのエピソードがつぎつぎと甦 り、たちまち文字がぼやけて追えなくなってしまう。いまもっとも社会人の涙腺を熱く弛ませ得る――といっても過言ではない傑作だ。なにをおいても読み逃してはならないと断言しよう。
うだがわ・たくや ときわ書房本店
「本の旅人」2016年4月号より転載
※便利な定期購読のお申し込みはコチラ