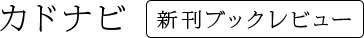2009年5月に施行された裁判員制度は、重大な刑事裁判の審理に市民から選ばれた裁判員が裁判官とともに当たる制度。それは一般市民が裁判に参加する、昭和3年から18年まで行われていた陪審制以来の大きな変革であったが、それから約七年、幾つかの是正を経てある程度の成果を上げつつも、裁判員の拒否率が高まるなど今もなお課題を残している。
日本の法制度を背景にしたリーガルミステリーは昭和の初期から書かれており、その歴史の上でも裁判員制度の発足は影響大だった――はずだが、従来とは一線を画するような作品が出てきたかといえば、そちらの変革もまだこれからといった感が強い。
本書もテーマは冤罪で、裁判員制度の影響は特に受けていない。無実の罪で獄につながれた人を救出しようとする話は古今東西を問わず、リーガルミステリーの定番中の定番といっていい。本書もその王道をいく作品であるが、一見オーソドックスに見えて独自の工夫が凝らされている。
物語は主人公の学生石黒洋平が母を病気で失い、その遺品を整理している際、自分の父が実の父ではないらしい証拠を見つけてしまうところから始まる。彼は闘病中の母を見捨てて離婚した父を問い詰め、それが間違いないことを確かめる。実の父の赤嶺信勝は検察官であったが、何と21年前、母の両親を惨殺した罪で逮捕され死刑判決を受けていた。彼はその赤嶺事件について調べていくうちに、社会派雑誌の編集記者・夏木涼子が冤罪の可能性ありと書いた記事を発見、彼女のもとを訪れ、当時の裁判の検察官――今は弁護士に転じた柳本のところに話を聞きにいくことになる。
柳本は痴漢冤罪事件に専念中とのことであったが、警察署の前で被害者女性の腕をつかんで告訴を取り下げるよう脅しているようだった。そのありさまを見た洋平は憤慨するが……というわけで、物語はそこからいったん赤嶺事件を離れて、痴漢にあった三津谷彩の事件の顛末に転じていく。そうしている間にも赤嶺は処刑されてしまうかもしれず、タイムリミットサスペンスは進行しているのだが、急がば回れじゃないけど、著者はそこであえて痴漢事件に踏み込み、その過程で冤罪事件を生む温床ともいうべき「代用監獄」問題を取り上げるなどして冤罪事件のシステムを掘り下げて見せるのだ。
その痴漢事件にも意外な真相が待ち受けているのはいうまでもないが、かように洋平と涼子がタッグを組んで赤嶺の冤罪を晴らすべく調査を続けるいっぽうで、赤嶺が気にかけていたという警察官の〝覚せい剤使用疑惑事件〟や、彼の検察官時代のトラウマになっている〝ヒ素混入無差別殺人事件〟の解明にも取り組むことに。
そうした多面的な調査活動から赤嶺事件の真相を逆照射していくとは、まさに新人離れした力業というべきか。直球勝負で赤嶺の冤罪を晴らしていくのを期待した読者は、最初は洋平たちがとんだ迷走を始めるようにも思われるかもしれないが、この著者はひと筋縄ではいかないということを改めて銘記していただきたい。
著者の下村敦史は2014年、5度目の候補で第60回江戸川乱歩賞を受賞して作家デビューを果たした。受賞作の『闇に香る嘘』は満州孤児である盲目の老人を主人公に、家族の秘密をめぐる謎解きを描いたサスペンスで、社会派ミステリー系の大型新人として一躍注目の存在となった。その後も通訳捜査官を主人公にした警察ものの『叛徒』、山岳ミステリーの『生還者』等長篇の他、短篇でも旺盛な創作活動を見せている。
今回も初のリーガルミステリーながら、冤罪という古典的な題材をベースに多彩なミステリー趣向を駆使して、最終的にはデビュー作と同様、感動的な家族の再生劇を演出、大型新人ぶりを遺憾なく発揮してみせた。今後このジャンルに挑む際は、ぜひ裁判員制度にも一石を投じてほしいものである。
かやま・ふみろう コラムニスト
「本の旅人」2016年4月号より転載
※便利な定期購読のお申し込みはコチラ