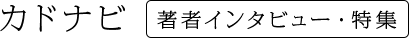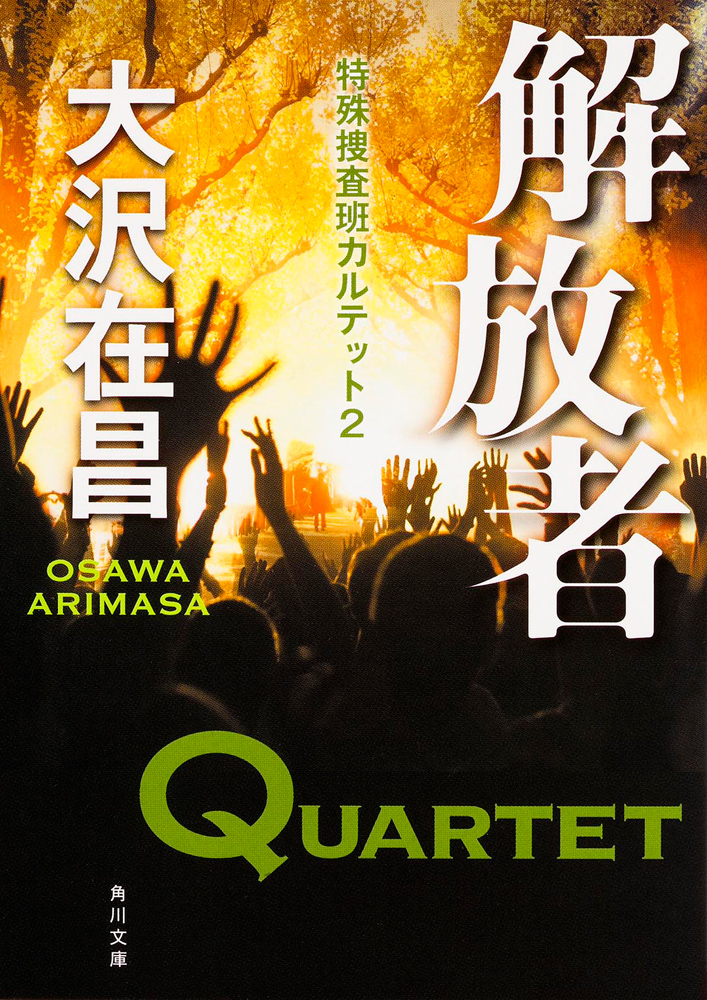
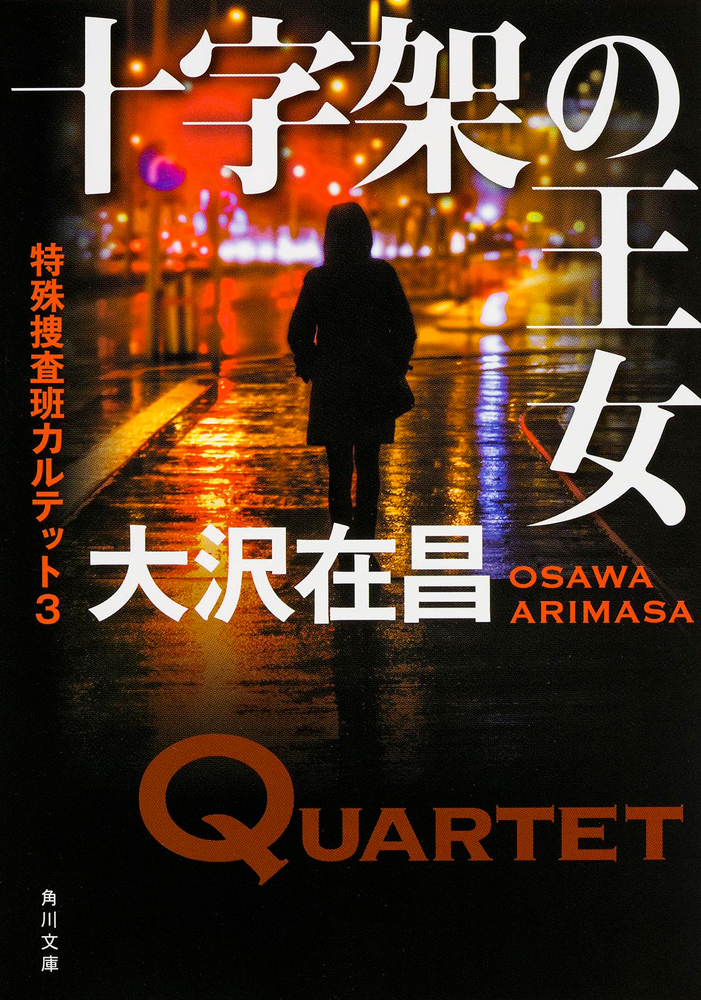

おおさわ・ありまさ
1956年愛知県生まれ。79年「感傷の街角」で小説推理新人賞を受賞しデビュー。91年『新宿鮫』で吉川英治文学新人賞、日本推理作家協会賞長編部門、94年『無間人形 新宿鮫Ⅳ』で直木賞、2014年『海と月の迷路』で吉川英治文学賞など受賞多数。近著に『極悪専用』『雨の狩人』などがある。
足かけ十二年にわたる連載が完結
――足かけ十二年という長い年月をかけた連載が終わり、ついに「カルテット」が完結しました。
大沢 途中空いている期間があったとはいえ、そんなに長くやってたんだ。連載開始時はいまの担当♂が社会人一年生、担当♀が中学一年生だったというんだから驚くね。
――このたび既刊の四巻を文庫化するに際して二巻に再編集し、連載が終わったばかりの「カルテット5」を第三巻として、九月から三ヶ月連続で刊行されることになりました。サブタイトルが「特殊捜査班カルテット」でメインタイトルがそれぞれ『生贄のマチ』『解放者』『十字架の王女』となります。
ところでこのシリーズを書くことになったきっかけは?
大沢 もともと映像化するという条件があり、それをもとにしてこの設定を決め、登場人物たちの背景も考えました。ドラマでは主演女優の関係で、女二人に男一人と、原作とは逆の設定になっています。ところが放送開始からしばらくして東日本大震災が起き、最終話まで放送できない地域もあって、ドラマとして非常に不幸な終わり方になったことは残念でした。幸いDVDボックスが発売されているので、興味のある方はご覧ください。
――いわゆるチームものですが、互いに敵対したり利害関係がからまったり、最初からチームワークのよい設定でないのが新鮮でした。

大沢 男二人に女一人という設定がまずありました。男のうちの一人は絶望、もう一人は怒りを抱えているというのがベースになっています。カスミは最初からかなりとんがった人物像で、目的のために自分の身体を利用するなどえげつないところもあり、手段を選ばない女性です。しかしタケルとホウにとっては母親であり聖女でもあるというキャラクターです。
実はインスパイアされたドラマが存在します。「モッズ特捜隊」という一九六八年から七三年まで制作されたアメリカのテレビドラマです。モッズというのはイギリスで五〇年代後半から流行した、若者たちの先端的なライフスタイルのこと。裕福な家庭に育った白人男性、スラム街出身の黒人男性、売春婦を母に持つ若い娘という三人組が登場します。臑に傷を持つ彼らが、ある刑事に脅されて若者たちの間で起きた凶悪犯罪の捜査をするという話でした。当時十二歳くらいでしたがよく見ていて、現代でそういうものをやりたいとずっと考えていました。
――制作数は百本を超えているようですが、日本では一シーズンのみの放送だったみたいですね。
大沢 すごく面白いドラマだった記憶があるけど、日本じゃ人気が出なかったんだな。
仲間が居場所に
――本書の主人公三人の性格をもう少し詳しくお願いします。
大沢 タケルは両親と妹を殺された過去があり、心の底には常に怒りをたたえています。それゆえに自分の感情をコントロールするすべを知らない。それをカスミが徐々に成長させていく側面も描いています。格闘など肉体的には強いけれど、精神的に脆いところがありますね。
――タケルが暴走しそうになったり、すぐ心が折れそうになったりするのも、そこから来た弱点ですね。
大沢 逆にホウは戦闘力はタケルにこそ劣るけれど、精神的に強いものを持っています。彼は中国残留孤児の三世で、幼いころに日本にやってきた。日本人には中国人と呼ばれ、中国人からは日本人と言われる。そのせいで確固としたアイデンティティを持てないことに悩んでいる。天才DJリンのボディガードを務めているころは、リンを守ることを心のよりどころにしていた。しかしリンのおまけという意識ばかりが強かったため、リンを失ったことで自分の人生に行きづまってしまう。そのホウに生きる目的を与えるように、カスミを設定しました。カスミはきれいで頭がよくて謎めいていてという理想の女性。アイデンティティの問題で出口がない苦しみの中にあったホウが、タケルとカスミ、そしてクチナワに出会って、反発しながらも仲間を得ることで居場所を見つけることができた。むしろ仲間が居場所になった。その要となっているのがカスミなんですね。
――二人がカスミを好きになるだろうという定番の三角関係がなかなか出てこないので、おやっと思っていましたが。
大沢 初めのうちは互いに信用していないし、反発の方が強くて、しかも任務もあったからそれどころじゃないという設定だった。徐々に融和してそれぞれの個性が立ってきて、感情の形が物語の中で見えるようになってくると、恋愛という要素が書きやすくなるということはありますね。
――文庫の二巻目後半あたりでしたね、カスミがとったある行動によって、特にタケルがめちゃくちゃショックを受けてしまう。
大沢 十年前、二十年前だったらそういう行動をしないヒロインを書いていたでしょうが、今は違う。もう少しわがままというか、自分の本能に対して忠実なヒロインを描きたい。きれいすぎるヒロインだと嘘くさくなっちゃう。だから、タケルとホウの二人に混乱を与えるような展開にしたりしました。まあ、先へ進めない恋愛だから、少女漫画じゃないけどいつまでも片思いという作りだね。

――実はその先を読んでいくと、カスミの方にも二人に対する思いがあり、それを断ち切るためだったのでは、ということが分かります。なるほどと思う設定でしたね。
さて、この作品の特徴を教えてください。
大沢 設定からしてある種ファンタジーというか、リアリティという意味ではぶっ飛んでいます。だからなのか、ライトノベルを意識したのかと散々聞かれたんだけど、それはまったく頭になかった。ただ若い人に読んでもらいたいという気持ちはありましたね。大沢在昌っておじさんの作家で、おじさんが読むものを書いている人なんでしょ、っていうイメージがたぶんあると思う。ラノベじゃないにしても、ジャンルは少し違うけど、たとえば辻村深月さんや道尾秀介さんを読んでいる世代、いわゆるバブル崩壊以降に物心がついた世代の書く作品を読む人たちは、読者としてちょっと違うなという意識がある。だからといってその読者たちが自分とは無縁であるとは思わないし、若い人にも面白いものは通じるはずだという気持ちはあった。こういう若者を主人公にした話で、おじさん無理しちゃってると受け止められたら痛いけれど、たぶんそうはなっていないという自信はあります。先ほど言った三角関係なんかは不変のものだしね。
スピード感が命
――若者もターゲットにしたことで、具体的にはどんな工夫をされたのですか。
大沢 この作品はスピード感が命だと思ってます。とにかく展開を早くスピーディにということを心がけました。中心人物は三人だから、三人の視点を交互に用いて、話をどんどん転がしていけた。会話を多くして章立ても短くしてね。特に男二人は理屈じゃ動かないというか動けないし、ほぼ感情で動いている。捜査といっても下調べするわけではなく、身体を張って出ていってどうだという世界。だから書いている最中は楽しくてしょうがなかった。「新宿鮫」の鮫島警部みたいに理屈をこねなくていいわけで。理屈から解放されている快感があった。
――取材には行かれたんですか。
大沢 最初に一回だけ、渋谷のクラブに行った。当時の「野性時代」編集長と、イントネーションが違う方の「クラブ」のおねえちゃんをつれて。そうしたら彼女らは身分証明書を持ってなかったので入れなかった。
――未成年者規制の問題ですね。
大沢 未成年って歳じゃないだろ、どう見たって三十近いだろって言ってもダメで、結局男二人で入ったけど、それじゃデカかヤクザかと思われるよね。
――一巻目の舞台となるクラブが後にもうまく使われているので感心しました。ほかに苦労したところはどんなところですか。
大沢 カスミの父親で犯罪帝国を築いた藤堂の描き方だね。藤堂の帝国の話を書き出すと、主人公三人の世界を超えてしまう。三人は現実との接点が小さい部分で生きている若者に過ぎないから。たとえばクチナワの視点から書けばすごく大きな世界を書けるけど。そこが「新宿鮫」と違う。鮫島なら麻薬組織のボスだって相手にできる。でもこの三人では売人か、せいぜいその上の奴くらいまでしか追いかけられない。そういう設定なので苦しかった。藤堂個人や組織についてどこまで具体的に見せられるか、いろいろ悩んだけど、結局見せることができないという結論になった。親子の問題になるので、最終的に藤堂本人が表に出てきて……という流れになる。
――部下の裏切りなど組織の揺らぎもあり、藤堂には滅びの願望みたいなものがあったのではないかと解釈しました。
大沢 あと、例によって何も考えずに書き進めたので、決着をどうつけるかで苦労した。そうしたら三人のうち誰が死ぬんですかなどとまわりが言いはじめてさ。三人全員が生き残ることはないでしょうとか、こいつらひどいなと思ったよ。俺がこんなに愛している登場人物を、おまえらそんなに殺したいのかってね。
――あれしかないという結末でしたね。
大沢 最後ああいうことになって、どうだ、ざまあみろという思いはあるね(笑)。
――三人の中ではホウがお好きだとか。
大沢 大好きな「ルパン三世」でも次元大介が一番好き。無口で頼れて、ちょっと大人で、一歩引いている奴。ホウにもそういうところがあります。おまえ自身はまったく違うだろう、おまえはルパンだよって言われるけどね。
――自分と違うキャラクターに憧れる?
大沢 そうなのかも。もっとも自分がルパンだとは思わないけどさ。
――最後に「カルテット」が完結して文庫化されることに対して一言お願いします。
大沢 個人的にも好きな世界の話です。「アルバイト・アイ」シリーズに近いファンタジックな設定で、もっと暴力的でとんがった戦いの物語です。実はそこにロマンスもあり、盛り沢山で贅沢な話だと思います。若い人も、本来の俺の読者も一番好きなアクション主体の物語で、同時に若者の迷いや悩みも、味付けとして入っています。ぜひこの世界を楽しんでください。
取材・文|西上心太 撮影|菅原孝司
「本の旅人」2015年10月号より転載
※便利な定期購読のお申し込みはコチラ