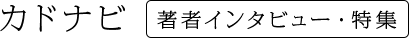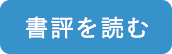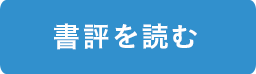澤村伊智 『ぼぎわんが、来る』
幸せな新婚生活を営んでいた田原秀樹の会社に、とある来訪者があった。取り次いだ後輩の伝言に秀樹は戦慄する。それは生誕を目前にした娘・知紗の名前であった。原因不明の怪我を負った後輩は、入院先で憔悴してゆく。その後も秀樹の周囲に不審な電話やメールが届く。一連の怪異は、亡き祖父が恐れていた“ぼぎわん”という化け物の仕業なのだろうか? 愛する家族を守るため秀樹は伝手をたどり、比嘉真琴という女性に出会う。真琴は田原家に通いはじめるが、迫り来る存在が極めて凶暴なものだと知る。はたして“ぼぎわん”の魔の手から、逃れることはできるのか……。
本体1,600円(税別) KADOKAWA

さわむら・いち
1979年生まれ、大阪府出身。東京都在住。幼少期より怪談/ホラー作品に慣れ親しみ、岡本綺堂作品を敬愛する。2015年、「ぼぎわんが、来る」(受賞時のタイトルは「ぼぎわん」)で第22回日本ホラー小説大賞〈大賞〉を受賞。巧妙な語り口と物語構成によって、選考委員から高評価を獲得した。新たなホラーブームを巻き起こす旗手として期待されている。
長編はいちばん好きな怖い話で
──第二十二回日本ホラー小説大賞受賞おめでとうございます。
澤村 ありがとうございます。想像もしていなかったので、まさか、という感じでした。いまはだいぶ落ち着きましたけど、最初は何かの間違いじゃないかなって。そもそも応募するために書いたわけではないですし。
──では、どうしてこの作品をお書きになったんですか?
澤村 話すと長いんですが、二〇一二年の春に会社を辞めて、はからずもフリーになったんです。さすがに最初は暇でした。そんなときに、小学校時代からの友人に「お前、暇なのか。だったら知り合いが趣味で小説を書いたから、読んでやってくれないか。感想は飲み会のときに言ってくれればいいから」と、原稿用紙一四〇枚くらいの小説を手渡されたんです。それがすごくつまらなかった(笑)。ボロクソにけなしてやろうと批評を書きかけたんですが、「待てよ」と思ったんですね。それまで出版社で編集をしたり記事を書いたりしていたんですが、ワンテーマで一四〇枚書いたことはない。その時点で水をあけられているんじゃないか。しかも飲み会で酔っ払いながら好き勝手言っている自分を想像して、これはないなと思ったんです。それで、自分でも同じ枚数の小説を書こうと思いました。同じ土俵に乗るためにその小説のなかにあるモティーフ、テーマを使って。それがそもそもの始まりですね。
──反応はどうでした?

澤村 そこそこ高評価でした。先に小説を書いた人にも「ここがダメだ」と堂々と言いたいことを言えましたね。
―──批評するために小説を書いたって人は初めて聞きました(笑)。
澤村 書いてから言ったほうがフェアだなと思ったんです。お前が書いてみろと言われる前に書こうと。そうしたら前述の友人が、面白いから何カ月かに一回この集まりをやろうと言い出したんです。友人も小説を書き始めて、途中、増員、欠員ありつつ、何カ月かに一回、いまも続けています。
──もともと応募する気はなかった、とおっしゃっていましたが、応募した理由は?
澤村 一四年の春までに、少ないときは二〇枚、多いときには一七〇枚くらいの作品をちょうど一〇作書きました。それで、このへんでぼちぼち長編を書こうかなと思ったんです。都筑道夫先生が『都筑道夫のミステリイ指南』で、なるべくはやく長編を書いたほうがいい、短編とはまったく違う経験になるから、とお書きになっていたのと、好きな作家の一人に殊能将之さんがいるんですが、デビュー作をお書きになったのがたしか三四歳のとき。僕も一四年当時ちょうど同じ歳でした。あの天才にはかなわないまでも、せめて長編を書き上げることくらいはやってみようと思ったんです。
──過去にも怖い話を書いてたんですか?
澤村 書いていないですね。超常現象が出てくる話はありましたけど。SF、コメディ、暴力的なものとか、いろいろです。でも長編を書くなら、いちばん好きな怖い話でと思ったんです。難しいことはわかっていましたし、ましてや長編ともなればどんだけ高い山なんだ! という不安もありましたが、すべってもいいからやってみようと思いました。書いてみたら評判が良かったので、ここで自分が満足して終わってしまったらもったいないな、と欲が出て、調べてみたら、あのホラー小説大賞が作品を募集している。正面から怖い話を書いたつもりだったので、ホラー小説大賞を受賞できたのは本当に嬉しいですね。
「幸せな家庭」が実は……
──『ぼぎわんが、来る』は、三〇代の夫婦と二歳の子どものいる家庭に、何かがやって来て、次々に怪異が起こるというお話ですが、一章ごとに語り手が変わっていきます。
澤村 一人称で書くほうが好きなんですが、当初予定していた三〇〇枚を、一人の人物の一人称で通すのは難易度が高い。だったら一人あたり一〇〇枚の三交代制にしようと思ったんです。
──第一章は家族を守ろうとする「イクメン」のお父さんが語り手ですね。ところが、第二章でかなり印象が変わります。
澤村 この形式で書くなら、章が変わるごとに前章をひっくり返したほうがいいと思ったんです。第一章のあらすじを一言でまとめると「幸せな家庭におばけが来る」。「おばけ」の設定をひっくり返して、おばけじゃなかったというのは禁じ手なので、あとは「幸せな家庭」しかない。それで、第一章で語り手は「幸せな家庭」だと信じ込んでいたけれど、実は……という展開にしようと思ったんです。そこで「イクメン」を思いつきました。同世代の友人、知人の多くは結婚して子どもがいるので、Facebookとかに子育ての様子をアップしているんです。楽しそうだなと思うんですけど、ほんとか?(笑)という単純な疑問も感じるんです。奥さん、子どもはどう思っているのかなと。それは何も現代の社会的病理ってわけでもなくて、楽しんでるのはおやじだけみたいな話は昔からありますよね。現代の話なので、イクメンといういまどきの言葉を入れておこうと思いましたけど。

──第二章は溜飲が下がりました(笑)。でも、イクメン批判というわけではないですよね?
澤村 モヤッとはしますけど、糾弾する側にはなりたくなかった。自分も子どもがいたらこうならないとはいえないですし、第一章でお父さんが家族を守ろうと必死になったのは否定できないんですよね。
──危機に陥った一家に力を貸すのが、おばけが「視える」真琴と、オカルト・ライターの野崎。さらに真琴の姉で能力者の琴子も参戦して、ぼぎわんと対決することになります。
澤村 真琴と野崎のキャラクターは、過去に書いていた短編にほんのちょっとだけ出てきているんです。お姉さんの琴子はもっと古くて、もともと学生のときから妄想をノートに書き留めたりしていたんですが、そのなかに女子高生として登場していました。琴子に関してはここに書いていない設定もたくさんありますよ。何しろ女子高生時代から知っているので(笑)。
おばけのどこが怖いのか
──もともと怖い話がお好きだということですが、ご自身で書かれるにあたって、こうしようと思われたことはありますか。
澤村 書くときに仮説を立てたんです。怖い話ってなんだろう。おばけってなんだろう。この二つの疑問に対する仮説を立てるところから考え始めました。まず怖い話ですが、英米怪奇小説の巨匠から、敬愛する岡本綺堂先生、現代の怪奇幻想小説作家の方々、実話怪談の書き手や、ネットのスレ住人まで、怖い話を上手に書く方たちに共通しているのは、怖い対象そのものは書かず、できごとと、それに対する語り手のリアクションを書いているところ。その二つを徹底して書けば怖いんじゃないか、と思いました。だからお話はいたってシンプルなんですよ。変なことが起こって、語り手が怖がって、また変なことが起こって、怖がって、という連続なので。
──おっしゃる通り、描かれるのは、不可解なできごとの連続です。では、その元凶と思われる「ぼぎわん」、つまりおばけについての仮説はどんなものだったのでしょうか?
澤村 おばけのどこが怖いのか。僕の仮説は、名前が怖いんじゃないか、ということなんです。由来でも実害でもなく、名前とそれが怖いものだという認識こそが怖い。作品のなかでも使った「トモカヅキ」なんてその最たるモノですよね。伊勢志摩に伝わるおばけで、海女さんとそっくりのかっこうをしていて、海女さんを海に引きずり込んで溺れさせる。「トモカヅキ」の意味は一緒にもぐる者。これだけだと自分としては怖くない。僕が怖いと思うのは、海女さんたちに恐れられていること、つまり「怖いという触れ込み」そのものなんです。そこから「トモカヅキ」という字面も、意味とは関係なく不気味に感じるようになる。
──「ぼぎわん」には古文書が出てきたり、由来が歴史的事実に関係していたり、いかにもありそうなんですが、澤村さんのオリジナルのおばけなんですよね?
澤村 ぜんぶ僕の頭の中で考えた話です。最初は民俗学の本から、実際に語り伝えられているおばけを拝借しようかなとも思ったんですが、そうしたら仮説の実地検証にはならないな、と。
──なるほど。「名前が怖い」という仮説を検証するためには、架空のおばけを登場させて、それが「怖い」ものとして一人歩きしていくかどうかを試さないと。
澤村 そうです。「ぼぎわん」が怖いものになっていったら、僕の立てた仮説は正しかったことになります(笑)。
──小説という言葉だけで組み立てるフィクションならではの実験ですね。最後に小説家としての決意をお聞かせください。
澤村 これまでどちらかというと流されて仕事をしてきたような気がします。でも、賞をいただいて、生まれて初めて一つの仕事にしがみつきたいと思いました。これからも高い頂に挑戦していきたいですね。たとえすべっても。
取材・文|タカザワケンジ 撮影|吉次史成
「本の旅人」2015年11月号より転載
※便利な定期購読のお申し込みはコチラ