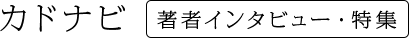かみなが・まなぶ
1974年山梨県生まれ。2004年『心霊探偵八雲 赤い瞳は知っている』でデビュー。同作から始まる「心霊探偵八雲」シリーズが、若者を中心に圧倒的な支持を集める。他著作に、「怪盗探偵山猫」「天命探偵」「確率捜査官 御子柴岳人」「浮雲心霊奇譚」「殺生伝」「革命のリベリオン」などのシリーズ作品、『イノセントブルー 記憶の旅人』『コンダクター』などがある。
神永学オフィシャルサイト
http://kaminagamanabu.com/
最終的に三つの物語が一つに

──「怪盗探偵山猫」シリーズの最新刊『怪盗探偵山猫 黒羊の挽歌』が発売されました。続いて単行本も刊行予定とのことで、放送中のドラマと併せて、山猫ファンにとっては嬉しいことが続きますね。『黒羊の挽歌』は中篇、短篇、短篇という3つのお話が最後にぜんぶつながります。これまでとはちょっと違う構成ですね。
神永 最初の段階では、最後にぜんぶつながればいいね、という話を編集者としていたくらいで、絶対につなげようと思っていたわけではないんです。そもそも、初めから書こうと決めていたのは、最後の短篇(表題作の「黒羊の挽歌」)だけなんですよ。
── そうだったんですか。意外ですね。
神永 ただ、雑誌「小説 野性時代」に連載するにあたって、最初はスタンダードな「怪盗探偵山猫」を読んでもらいたいと思いました。初めての連載になるので、トリッキーな話を書いたら読者が戸惑うだろう、と。それで、初めに書いたのが第2話の「羊の叛逆」なんです。書いた順で言うと、第2話、第1話、第3話ですね。本来は短篇4篇で構成する予定だったんですが、第1話の「羊の血統」の話が広がってしまい、思っていたよりも長くなってしまいました。
──「羊の血統」はこのまま長篇として最後まで行きそうなくらい、構えが大きい物語ですね。冒頭、ベネチアンマスクをつけた若い女性が、半グレの男たちに追われて走ってくる。格闘技に秀でた女性で、山猫の世界にまた一人、魅力的なキャラクターが加わったと思いました。
神永 一度は短篇として仕上げたんですが、ここまでインパクトのあるキャラクターを短篇で使ってしまうのがもったいないと思ったことと、話自体を膨らませて厚みを持たせたいということもあって、少し長くなりました。いつも通り、山猫も自由に動き回ってくれましたし。ただ、今になってみると、長篇にできる話だったかもしれないですね。もったいないことをしました(笑)。
── ほかに短篇を2つ加えて一冊になっているわけですから、読者としては得をした気分になれますね。3つの短篇が結果的に一つにつながるということは、神永さんのなかで、無意識のうちに一つの世界があるのかな、と思ったのですが、いかがですか。
神永 考えながら書いているうちは進まないんですよ。無意識まで落としていかないと筆が乗らない。書いていると、自然と考えずに書けるポイントが出てくるんです。それが別々に書いた物語の世界観がつながった瞬間なんでしょうね。ですから最後に書いた第3話は、書き始めたら早かったです。でも、無意識に書いているから、書いた内容を自分で覚えていないことも多々あるんですよ。
── それだけ無意識の領域に下りているってことですね。
神永 締切に追われてるってこともありますけど(笑)。
10周年を迎えた山猫

── 山猫の第1作が出たのが2006年。今年でちょうど10周年なんですね。山猫というキャラクターとのお付き合いも、ずいぶん長くなりました。
神永 付き合いが長いので、自然に動き出してくれる部分はありますね。正直、山猫がなにを話すのか、台詞は考えたことがありません。こんなことを言うのか、こういうことをするのか、と作者である僕も驚くことがあります。背景になる事件や状況に山猫を放り込んであげると、山猫が勝手に動いてくれる。執筆中は、こういう状況になったらおそらく山猫ならこんなことをするだろう、と考える間もないほどです。この本でいえば、第三話は特にそんな感じでしたね。刑事の犬井がバー〈STRAY CAT〉に入ってくる。そこで女とぶつかる――。なぜだろう、と自分でも思っていたんです。それが後になって、ああ、そうか、あのときにぶつかった女だったのか、とつながってくる。そういうことが自然に起きてくるんです。シリーズを長く書いていると、物語がひとりでに進んでいくような感覚がよくありますね。そこに持っていくまでが一苦労ですけど。
── バーと言えば、山猫はバーのマスターでもあるんですよね。神永さんは実在の人物や場所を組み合わせて小説をお書きになるそうなんですが、バー〈STRAY CAT〉のモデルはあるんですか?
神永 ええ。私鉄沿線の某所にあるバーがモデルです。お酒はなんでも揃っていて。実は、僕はあまりお酒が飲めないんですが、そう言ったらマスターが「メーカーズマーク」というバーボンを出してくれました。これでも舐めてろ、と言われて。カウンター席とわずかなテーブル席しかないこぢんまりとしたお店で、マスターは客がいるにもかかわらずお酒を飲んだり、たばこを吸ったりしている。この雰囲気、面白いなと思ってモデルにしました。ちなみにそのバーは、マスターが気まぐれに作るパスタが絶品なんですよ。
── 小説のなかではあまり細かく描写はされていませんね。
神永 ええ。読者が想像する余地を残しておきたいんです。小説の面白さというのは、読者が自由に想像できるところだと思うんですよ。それぞれの心のなかにあるバーのイメージを投影して読んで欲しい。だから小説のなかで、規模や雰囲気など、具体的な描写は最低限にして、あとは想像してみて、ということですね。〈STRAY CAT〉は、下北沢にあるという設定なので、下北沢のバーに入ったときに「山猫がいそうだな」と思ってもらえれば嬉しいです。
── 主人公である山猫は神出鬼没の窃盗犯で、窃盗のついでに悪事を暴く、とてもスマートなキャラクターです。作者である神永さんに似ているところはありますか。
神永 ないですね。むしろ、山猫の姿は僕の願望かもしれません。酒に強く、気軽に女を口説き、下世話な話も笑いとして通せる。羨ましいですね(笑)。唯一、似ているのは音痴なところかもしれません。
── そうなんですか?
神永 ええ。高校生のときにバンドをやっていたんですけど、コーラスは入れなくていいって一人だけ言われたんです(笑)。
―― では、好きなところは?
神永 僕が山猫で好きなところは、自分が犯罪者だと堂々と認めているところ。あれだけ悪事を働いておいて、「俺は正義のために盗みを働いている」なんて言い出したら「それはどうなんだ?」と、疑問を持たれると思います。山猫は自分は悪だと認識している。そのうえで、最後には人を幸せにしている。僕の作品から出てきたキャラクターながら、そこが気に入っています。
── 今回は、女子高生の怪死事件から物語が始まりますが、山猫がからむ事件を考えるうえで、ご自身で決めているルールのようなものはありますか。
神永 一つは現実からかけ離れないこと。現実から離れすぎてしまうと、「僕たちには関係ない」と読者に思われてしまうのではないかと思っているからです。現実世界とつながっていて、かつ、そんなに悪いことをしているやつなら盗まれても仕方がないよね、と読者に納得してもらえるような事件を考えるようにしています。山猫は泥棒ですから盗みが仕事ですが、誰からでも盗むわけではない。いくらお金持ちだからといって、まっとうな仕事をしている人から盗んでしまったら物語がブレてしまう。読者にカタルシスを感じてもらうためには、こいつからなら山猫が盗んでもいいと思ってもらえるだろう、というところが重要なポイントですね。
── 世の中にはさまざまな〝悪〟がありますが、そのなかでもどんな〝悪〟でしょうか。
神永 山猫が盗むことで相手がダメージを受け、それがきっかけで、一般の人たちの被害が減るような〝悪〟ですね。実は、山猫の敵選びはすごく難しい。たとえば、政治家と企業が結びついて賄賂のやりとりがあったとしても、一般の読者から見れば世界が遠すぎて、勝手にやってれば、となってしまう。
──「現実から離れすぎない」というのは、読者の日常からの距離なんですね。読者にとって身近に感じる〝悪〟を山猫はターゲットにする。
神永 そうですね。かつ、いまの世相を考えて、誰もが納得できる悪じゃないと難しいですよね。あまり小物だと敵にならないですし。
犬井と山猫の「信念」
──第3話の「黒羊の挽歌」の視点人物は特別捜査班の刑事、犬井ですね。『怪盗探偵山猫 虚像のウロボロス』に登場したときには「狂犬とも綽名される男だ。誰も寄せ付けず、捜査は全て単独行動。犯人逮捕のためなら、手段を選ばず、今まで何人もの容疑者を病院送りにしているらしい」と描写されています。短篇集『怪盗探偵山猫 鼠たちの宴』のなかにも登場する強烈なキャラクターです。
神永 犬井も山猫も価値観が極端なんですよ。じゃあ、その極端さは悪なのか? というと、そうではなく、彼らなりの信念が極端な価値観をつくっている。犬井の信念は「犯人を捕まえるためには何をやったっていい」。犯人さえ逮捕すれば「あとは知らん」。
── 間違ってはいないけれど、たしかに極端ですね(笑)。
神永 極端なキャラクターが入ることで、山猫と対比もできますし、お互いに信念を持って行動していることもわかっているので、言葉を交わさずとも、相手の行動を読み合って、結果的に共通の敵を倒すこともできる。二人が組んだら最強のコンビだと思いますね。刑事と泥棒ですから、絶対にコンビにはなりえませんが。
── 犬井が登場したことで「怪盗探偵山猫」のシリーズが、新たな段階に入ったのでは、と思いました。
神永 そうですね。犬井は僕自身、とても好きなキャラクターなんです。ハードボイルドの雰囲気をまとっている。以前、小説のなかでも書きましたが、犬井は事件の背後に何があるかということにはまったく興味がない。「組織のなかで、あいつを追えと言われたから追う。以上」。そして、とても優秀なんですよ。
── 優秀な猟犬のような一面がある。
神永 だから、周囲から一目置かれ、単独行動が許されている。読者も認めてくれている。山猫のライバルとして今後、たびたび登場するんだろうなと思います。
── 雑誌記者の勝村は、「怪盗探偵山猫」シリーズがスタートしたときから山猫と行動をともにしていて、シャーロック・ホームズに対するワトソン的なポジションにありますね。今回、勝村が徐々に変化してきているなと思いました。たくましくなってきたような気がしますね。
神永 だんだんアグレッシブになってきました。いままでは山猫に振り回されているばかりだったのですが、少しずつ機転が利くようになってきた。
雑誌記者の勝村は普通の、つまり一般人の目線を持っている。だからこそ山猫の異様さが際立つという意味でも、重要な登場人物です。同時に、勝村は唯一、山猫に意見できる人物なんです。今後、二人のコンビの距離感はどんどん変わっていくでしょうね。「怪盗探偵山猫」シリーズは、勝村の成長物語みたいなところもあるので、これからもその変化を描いていければと思っています。
── 次の「怪盗探偵山猫」シリーズは、長篇単行本で刊行予定なんですよね。現在、執筆中とのことですが、どんな作品になりそうか、少しヒントをいただいてもいいですか。
神永 キーワードは「申」です(笑)。実は、「怪盗探偵山猫」シリーズは、2作目以降のサブタイトルが干支にちなんでいるんです。『虚像のウロボロス』のウロボロスは蛇。次が『鼠たちの宴』。去年は未年だったので、『黒羊の挽歌』。今年は申年なので「申」なんです。まだ書き終えていないので、物語がどう転んでいくのか、僕にもわからないんですが。
── 書く前にストーリーはできあがっていないんですね。
神永 3年くらい前までは構成を細かく決めていました。しかし、最近はあえてそれを捨てています。状況をつくっておいて、先のことは考えずに書き始める。すると、思いもよらない人物のキャラが立ってきたり、予期せぬ展開になったり、意外なテーマが浮き彫りになったりするんです。いまは小説を書くという〝現場〟を大事にしています。
── ますます面白くなりそうですね。次作も山猫の活躍を楽しみにしています。
4つのキーワードで読み解く「怪盗探偵山猫」 の世界
神出鬼没の窃盗犯、山猫の性格をより強固に、また魅力的なものに形作っているのが、捻りの利いたキャラクター設定や小道具です。神永さんご自身のこだわりについても伺ってみました。
【 ウイスキー 】
近年、ハイボールがブームだが、山猫はそれ以前、初登場した10年前からウイスキーを飲んでいる。愛飲する銘柄はジャックダニエル。「山猫にハードボイルドな空気をまとわせたかったんです。ジャックダニエルは僕が学生時代に飲んでいた唯一のウイスキーでもあります。その当時、映画『セント・オブ・ウーマン』でアル・パチーノが〝ジョン〟と愛称で呼んでいたことにあこがれていたんです」
【 チョコレート 】
山猫は一仕事する前にチョコレートを食べることが習慣になっている。お酒を愛する山猫がチョコを食べるのはなぜ?「僕自身がバーで教わったんです。小説のなかにも書きましたけど、ウイスキーを頼んだら、チョコがおつまみで出てきた。『チョコはないでしょう』と言ったら、『ウイスキーボンボンってあるだろう? チョコレートとウイスキーは合うんだよ』と言われて。なるほどと思ったんです」
【 音痴 】
山猫は実に気持ちよさそうに歌うのだが、それが大迷惑なほどの音痴。「歌も完璧だったらただの嫌なやつですよね。一つくらい欠点があったほうがいいんです。しかも音痴は本人が一生懸命になればなるほどおかしい。曲は物語に合わせて決めていますが、いつも悩みますね。みんなが知ってる懐メロですが、もしかすると曲から山猫の年齢を〝推理〟できるかもしれません。深読みしてみてください」
【 下北沢 】
山猫が世を忍ぶ仮の姿として選んだのが下北沢のバーのマスター。下北沢という街を舞台に選んだのはなぜ?「一時期、下北沢でよく飲んでいたんですよ。劇場が多いこともあって演劇をやっている人、何かをめざしている人が多い。街自体がパワーを持っていて、いろいろなものが混在している。いま、そういう街は少なくなりましたよね。山猫にはそういう環境が合っていると思います」
怪盗探偵山猫シリーズ好評既刊



取材・文|タカザワケンジ 撮影|ホンゴユウジ
「本の旅人」2016年3月号より転載
※便利な定期購読のお申し込みはコチラ