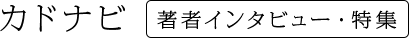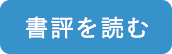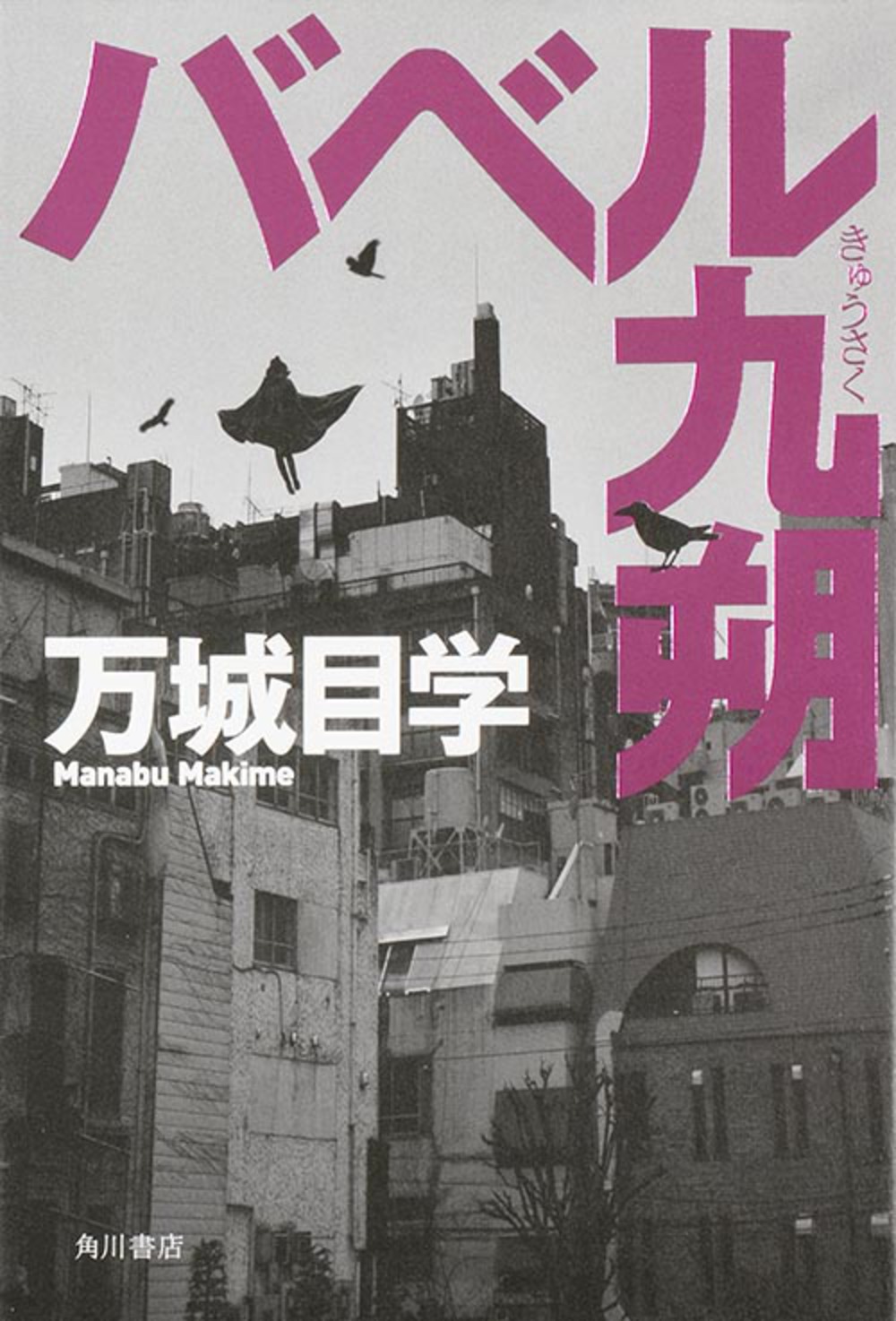

まきめ・まなぶ
1976年、大阪府生まれ。京都大学法学部卒。化学繊維会社勤務を経て、雑居ビル管理人を務めながら小説家を目指す。2006年に第4回ボイルドエッグズ新人賞を受賞した『鴨川ホルモー』でデビュー。著書に『鹿男あをによし』『ホルモー六景』『プリンセス・トヨトミ』『かのこちゃんとマドレーヌ夫人』『偉大なる、しゅららぼん』『とっぴんぱらりの風太郎』『悟浄出立』などがある。
「3分の1自伝的小説」

――『偉大なる、しゅららぼん』以来、久々の現代もの、長篇ですね。
万城目 5年ぶりになります。
――今回は主人公が小説家志望。自伝的小説、と銘打たれてます。
万城目 取材に来てくれた方から「自伝的小説じゃない!」って言われたんですよ。僕のなかのイメージとしては、チャールズ・ブコウスキーの『ポスト・オフィス』。小説家になる前に郵便局に勤務していたブコウスキーの、くさくさした毎日を書いた小説ですけど、あんな話を書いてみたいな、と。あれを自伝的小説と言うなら、これは絶対違うから、「半自伝的」のほうがいいのかな。額面通りにとられて、怒られるのも困るので。どう思いました?
――万城目さんが普通に自伝的な作品は書かないだろうな、と予想はしていましたが、万城目さんの作品を一冊でも読んだことがある方なら、ニヤリとするんじゃないでしょうか。でも、出だしはかなりリアルというか、まさに自伝的ですよね。
万城目 大学を出て2年働いて、辞めてから小説家になるために雑居ビルの管理人をやってました。その点は当時の自分を忠実に書いていると思いますね。管理人は作家デビューした後も続けて、『プリンセス・トヨトミ』の連載を始めるまでやってたんですよ。
――そうなんですか。章タイトルはビル管理人の仕事から採っていますね。
万城目 そうです。実際の業務内容とか、ある程度は本当のことを書いてます。脚色はしてますけど、全体の3分の1くらいは自分の経験ですね。
――ということは「3分の1自伝的小説」(笑)。もともとは「野性時代」(現「小説 野性時代」)の特集のときに書いた短篇がきっかけだそうですね。
万城目 7年前になりますね。「野性時代」で僕のことを特集していただいたときに、何でもいいから一つ短篇を書いてください、と言われまして。僕は書くのが遅くて、短篇をためて本になるまでにかなり時間がかかりそうなので、じゃあ長篇の冒頭を書かせてください、と。
――これまでの万城目さんの作品を考えると、3分の1とはいえ自伝的な作品をお書きになったことに驚いたんですが、それはなぜですか?
万城目 それはたぶん、最初に書いたときが、気持ち的に「お試し」だったからだと思いますよ。初めから連載でって言われたら身構えるから、ひょっとしたら、アイディア段階でこれは無理だからやめると言ったかもしれない。先を約束しないスタンスだったので、ちょっと自伝っぽくやっちゃおうかな、みたいなことだったんじゃないですかね。
――そして満を持して「文芸カドカワ」での連載が始まったと。
万城目 連載を始めたときもすごい弱気だったんです。でも、これは絶対に面白い話になるから、と担当さんから言われて。なんでそんなことわかんの、と思いつつ(笑)。一章を書いてからけっこう経ちましたから、また一章から感覚を取り戻しがてら書き直しました。
秘密を持った3階の人物

――7年前の時点ですでに「バベル九朔」というタイトルだったんですよね。
万城目 そうです。イメージとしては、雑居ビルの管理人をやっている小説家志望の男が主人公。個性的なテナントの人とやりとりしつつ、泥棒が入りつつ、という現実にありそうな話を書こうと思っていました。
――バベル九朔はつぶれそうなテナントばかりが入っている雑居ビル。店子もちょっと変わった人ばかりです。
万城目 『めぞん一刻』のように、2階が双見、3階が蜜村、4階が四条と、名前が階数と符合しているんです。なかでも3階の蜜村さんの「蜜」には秘密の「密」をかけていて、何をやっているかを謎にして書いたんですよ。
――それが今回の長篇で生きていますね。蜜村さんは物語の鍵を握る重要な人物です。
万城目 それで言うなら、主人公は5階に住んでるから「ゴ」から始まらないといかんわけですよ。でも、主人公の名前は、何も考えずに「九朔」にしてしまった。そこにも整合性が欲しい。そのへんが、新たに書き直すにあたり、鍵になりました。多くは言えませんが。
――「バベル九朔」はテナントビル名ですけど、意味ありげで、謎めいています。
万城目 後付けなんですよ。最終的にバベルっぽい高い塔が登場する話になったのも、語感に引っ張られてそうなったというだけで。バベルには人間の傲慢を打ち砕くという、教訓的な意味がありますよね。まあ、それも後付けですけど(笑)。
――欧米でバベルっていうと、空想的、実現不可能な計画という意味らしいですね。ヘブライ語でごちゃ混ぜって意味もあるそうで、雑居ビルを連想させますよね。
万城目 マジですか……。初耳ですよ。
――なんと(笑)。不思議な符合がまだまだ見つかるかもしれませんね。
無駄を認めてあげたい
――万城目さんの作品では京都とか奈良、大阪などの「場所」が重要な役割を果たすことが多いですよね。ところがこの作品は場所が特定されていません。
万城目 最初から、ビルの中の閉鎖的な空間で、一歩も外に出ることなく展開する物語を書くと決めていたんです。雑居ビルの管理人をしていたのが東京なので、東京っぽくはあるんですが、街とか歴史とかを使って書く気は起こらんし、これが僕が東京を舞台にした精一杯という感じですね。
――小説家になれるかどうかわからないけれど書いている、という時期の不安定な心が生々しく描かれていると思いました。
万城目 そのときの感覚そのままなんで、そのへんは簡単に書けるんですよ。日記を書くのに近い感覚です。
――では、むしろ大変だったのは、経験したことにどう味付けをしていくか。
万城目 そうですね。味付けの部分を、非現実的な話に委ねたんですね。そこがないと書ける気がしなかったです。現実的な話だけだと面白くないというか、夢を追う若者とかは、よくある要素だから面白くできる気がしなかった。自分のなかの「大丈夫だ」というゴーサインが出ないと書けないので。どうふくらませれば一冊にできるかな、と考えました。
――テナントビルなので、店名だけも含めいろんなお店が出てきます。それも偏ったお店ばかりで、広島でもないのにカープ専門店「コイする惑星」とか(笑)。
万城目 昔、大阪の地元にジャイアンツショップがあったんですよ。よくこんなところにつくるなと思って、その記憶が色濃かったので使ったんです。その店は長続きしなかったですけど。店を考えるのは楽しくて、見直すたびに増えていくんですよ。こういうのもあるな、と。
――つぶれた店もたくさんある。夢の残骸、無駄の山なんですよね。
万城目 昔から効率良くとか、ストレートに成功する人生とか、そういうものにあんまり価値を感じない。無駄を認めてあげたい。うまくいってない人のほうが好きなんです。
「詰め将棋」と「デッサン」
――自伝的要素以外の3分の2は、すでに亡くなっている祖父の「大九朔」と、「カラス女」との間で主人公が翻弄されていきます。「カラス女」は黒ずくめでナイスバディーの女性なんですよね。サングラスを取ると……。
万城目 7年前に書いたとき、サングラスをかけさせておいてよかった。イメージでは、『ルパン三世』の不二子ちゃんみたいなドロボーのつもりだったんです。カラスっていう仇名を与えるためだけに黒ずくめにして……、いや、違う。今、読み直したら、全身真っ赤な服を着た女だと書いてる……。衝撃です。ということは、当時はカラスのイメージはなかったということですね。すみません、著者がこんないい加減で。とにかく、新たに二章を書くとき、彼女がサングラスを外したら、一気に「カラス女」の存在感が増して――その工夫を思いついたときには自分でも嬉しかったですね。
――4四階の私立探偵、四条さんの言動もユニークです。探偵は出てくるわ、謎の美女は出てくるわで、ハードボイルド的な部分もありますよね。
万城目 それもきっと、チャールズ・ブコウスキーですね。『パルプ』。だめ探偵の話で、すごく好きなんです。設定にはブコウスキーへのオマージュがほんの少し入っていて、だめな人しか出てこない。ブコウスキーの小説にはだめな人しか出てこないから。
――なるほど。しかし、お話をうかがっていると、書き継いでいく過程で、予期しない方向へ展開していったようですね。
万城目 作家になりたての頃は、物語が最後まで決まっていないと不安で書けなかったんですよ。でも、今は、以前だとビビってゴーサインを出せなかったところを、なんとかなるだろうって行けるようになったとは思いますね。行けるといっても、ひたすら、一人で詰め将棋をしているような感じでしたが。この展開だと何手先で詰まる、やめとこ。こっちだ。やめとこ。こっちだ。その連続でしたね。それと、デッサンをしてるイメージ。あわーい鉛筆の線でね、はっきりとしないようにごまかしながらデッサンをするんです。でもときどきは物語の展開上、実線で、線を決めてくっきり描かないといけないところがあって、あとあとになって、その線に接続できる描き方が見つからず、うーんと悩む。いままで、こういうイメージで書いたことがなかったですね。いちばん苦しかったのは、主人公が、見知らぬ湖に突っ立っているシーンからです。何もない白地図に、山をつくり、道路をつくり、建物をつくり。そこに女の子が出てくるけれど、いかにあやふやな会話で、あわいデッサンのラインのまま次へとつなげるか。
――いかにあいまいにしておくか。しかしそのおかげだと思いますが、理屈では説明がつかないゾクッとするところもあるし、先が読めない面白さもあります。どこまでいっても騙されている感もあって。
万城目 この物語をどうとらえればいいんだろう、と書いた僕自身も思いますね。スカッとしたわかりやすい面白さじゃなくて、すぐには消化できない何かが残る。僕自身の印象は「奇書」なんですけど。
――現実と非現実。ウソとホントの混じり合い方が絶妙なんです。
万城目 こういう物語の作り方をしたのは初めてなので、こういうのもありなんだ、というのは発見でしたね。クリストファー・ノーランって映画監督がいますよね。『ダークナイト』とか『インセプション』の。僕はノーランの誠実さが好きなんです。大風呂敷を広げても、最後まで観客に説明しようとする。『バベル九朔』も最後まで誠実に、と思って書いていました。
――直感や偶然を採り入れつつ、誠実に書くという万城目さんの姿勢は、『バベル九朔』という作品の印象と重なります。デビュー作の『鴨川ホルモー』が2006年刊行ですから、今年は作家生活10周年の節目でもあります。記念すべき年にふさわしい作品だと思います。
万城目 10年と言っても実感はないですね。僕のなかでは4、5年しかやっていないような気がします。たぶん冊数の問題だと思うんです。小説はまだ9冊目だから。人によっては3年くらいで突破するだろうし、10年で9冊はちょっと残念ですもん。
――次の10年はペースが上がりそうですか。
万城目 変わらないんじゃないですかね。同じ同じ(笑)。
取材・文|タカザワケンジ 撮影|ホンゴユウジ
「本の旅人」2016年4月号より転載
※便利な定期購読のお申し込みはコチラ