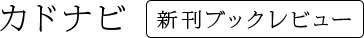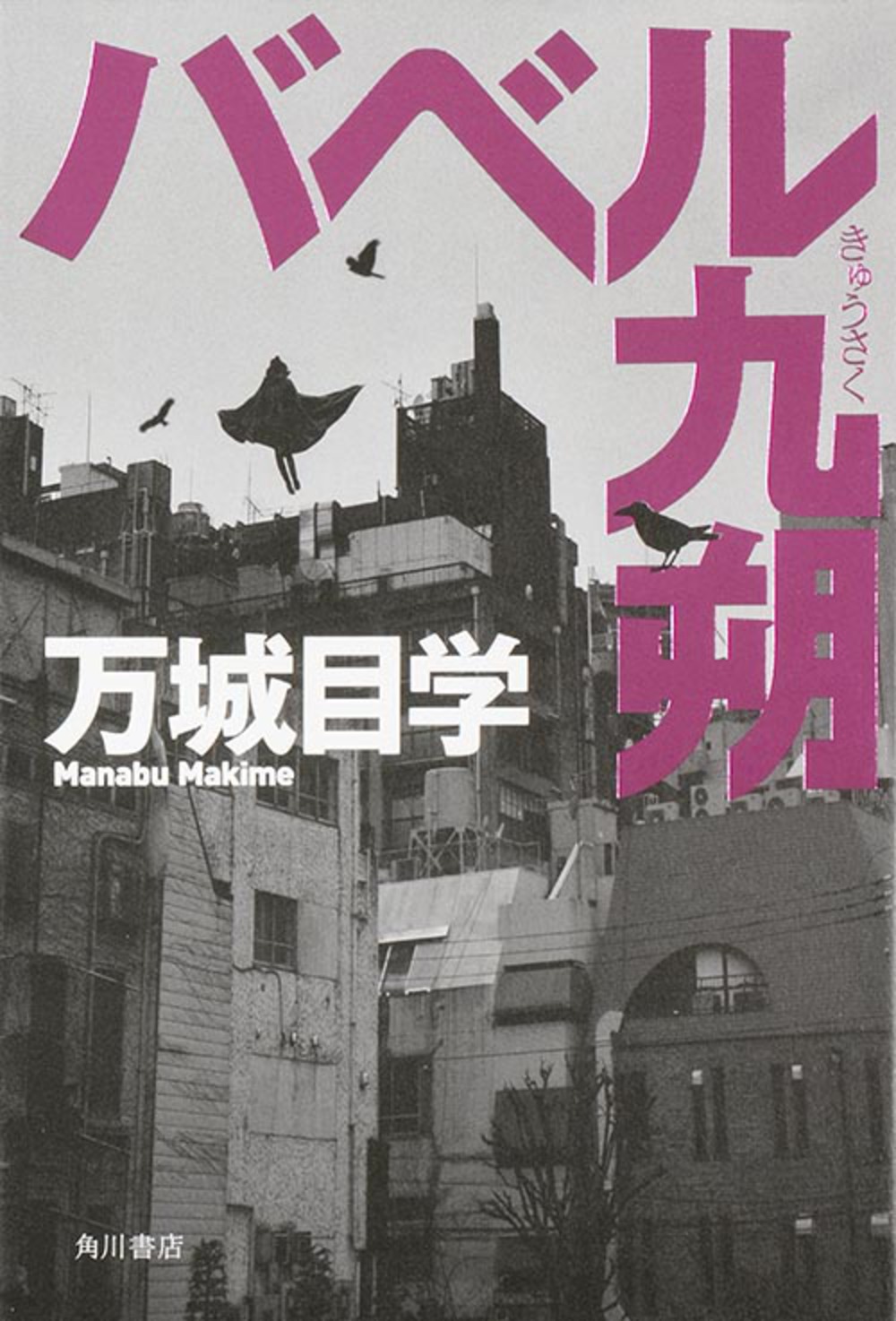今年、作家生活10周年を迎える万城目学氏。そのタイミングで発表された新作長篇『バベル九朔』は、まさに節目の年にふさわしい記念碑的な作品だ。デビュー以来関西地方を舞台にし、日常生活の中に荒唐無稽な出来事が紛れ込むファンタジーを得意としてきた著者だが、昨今は時代小説や中国古典を下敷きにした連作に挑戦。現代を舞台にしたファンタジー作品は5年ぶりだが、これが実に、深みを増した作品なのである。
主人公、九朔満大は大学卒業後に就職したものの、小説家になりたくて親に内緒でこっそり退職。母親が祖父から受け継いだ5階建ての古い雑居ビル〈バベル九朔〉の最上階に引越し、管理人をしながら原稿を書いては応募する日々を送っている。明記はされていないが九朔の実家は関西にあり、雑居ビルは東京のどこかの街の線路沿いに建っている模様。
ビルのテナントは居酒屋や画廊、探偵事務所などで、彼らとの関係も良好だ。だが、階段でサングラスに黒ずくめのグラマラスな女性とすれ違った。数日後、各階に泥棒が入った形跡が見つかり、例の女が窃盗団の一員であると知った九朔。だが、ビルの屋上でその“カラス女”と再び出会いなぜか詰問され逃げてもがいて苦しんで気づけば――そこは巨大な塔がそびえる異世界〈バベル〉だった! 塔の中に迷い込んだ九朔は、そこにいた少女や追ってきたカラス女、なぜかこちらの世界にやってきた4階の探偵、四条さんらと〈バベル〉の謎をめぐって大騒ぎ、やがては混乱を解決するための大きな決断を迫られる。いつもながらのイマジネーション豊かな冒険と緻密な世界づくりにニヤニヤしつつ、いくつかの新たな試みに嬉しい驚きをおぼえながら読み進めることになる。
新しい試みというのはまず、関西以外の場所を舞台にしていること。また今回は場所を明記していない点も、実在の土地の持つイメージに頼らずに世界を構築するという、いつもと違う工夫が感じられる。珍しく自伝的であることも注目ポイント。というのも万城目氏自身、会社を辞めて上京し、親戚の持つビルの一室に住んでひたすら原稿を書いては新人賞の応募に励んだ時期があるからだ。以前インタビューで語ってくれたのだが、一度も一次選考を通過しないまま2年が経ち、これが駄目だったら再就職しようと決めて書き上げたのがデビュー作『鴨川ホルモー』だったという。つまりまったく芽が出ず諦めを感じはじめた九朔の姿は、当時の著者そのものなのである。また、小説家になりたいと願う九朔の心情が描かれている点からも分かる通り、「夢を見る」「何かを創る」ということが本作のひとつのテーマでもあり、これがジワジワと読み手の心にも沁みてくるのだ。
これまでは日常の中に非日常が紛れ込む話が多かった著者が、完全に異世界を舞台にした点も新鮮だ。全篇を通して主人公は一歩もビルの外に出ないのに、読者の眼前には壮大な景観が現れる。ビル内でイマジナリーな世界が広がる構造は、脳内で夢や創作物が作り上げられる様と重なり、そのなかで九朔も自分の内面と向き合うことになる。さらには祖父が〈バベル九朔〉を建てた思い、異世界〈バベル〉が成立した経緯、そして最終的に九朔が下さねばならない大きな決断にも、夢や創作というモチーフが絡んでくる。
作中、ある人物が「無駄を見る」という。「夢を見る」といえば聞こえはいいが、結局うまくいかなければ無駄になる、つまり「無駄を見る」というわけだ。なんとも残酷なこの表現に九朔も言葉を失う。しかし、無駄を見るのは悪いことではないと、本書は訴えてくる。ほろ苦さと爽やかさが入り混じるラストシーンは、創作に打ち込んだ九朔の時間を肯定するものだ。こんなふうに創作というものを肯定する作品で10周年を迎えた著者。今後の新たな挑戦への期待が膨らまないわけがない!
たきい・あさよ ライター
「本の旅人」2016年4月号より転載
※便利な定期購読のお申し込みはコチラ