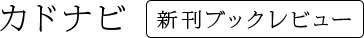俳優の吉永小百合さんが30年にわたって続けてきた原爆詩の朗読。広島、長崎の被爆は、人類の惨禍である以上に、人間の命が経験しなければならなかった、言葉では語りつくせない悲劇であったことをあらためて知らされる。言葉を越える経験、それはどうすれば伝えることができるのだろう。戦後70年の時間がたち、次世代への記憶の継承は重くのしかかった課題である。
敢えて十代の読者を対象にした「つばさ文庫」に、吉永さん自らが選び、読み続けてきた長崎の原爆の記録が、新たに加わった作品もふくめて収められた。第一部は、被爆後も命尽きるまで平和を希求して筆を執り続けた医師、永井隆の思いを継いで、娘の筒井茅乃が長じて綴った「娘よ、ここが長崎です」。自身の娘に語り継ぐかたちで綴られた記憶は、1945年8月9日の長崎で何が起きたのか、そしてその後も続く苦悩のありようを、幼い少女の心の軌跡として立ち現わせる。死に向かいゆく父の姿、そしていまや母もなく、兄と二人っきりで取り残される心もとなさ……。同時に、日々の営みに存在するささやかな喜びもまた、現実の思い出として書き綴られる。原爆の記録が、まぎれもなく「命の記録」であることが伝わってくる。
なにものにも代えられない命への切ないまでの思いが、「誰か」の物語を「自分たち」の物語へとかえてゆく。第二部の手記も原爆詩も、けんめいに命をその手に握り続けようとする精神の純粋なまでのひたむきさを、むごさ悲しさゆえに一層強く、読者の心に刻印する。それは読者にとって苦しいものである以上に、人間であることの証としてなにかしら深いあたたかい感情をともなって、心のひだに寄り添わせる。そのような物語へのまなざしは、スタジオジブリ作品の背景画を手がけてきた男鹿和雄さんの絵がかもし出す、命への限りないやさしさと重なっている。被爆したクスノキが、ふたたび豊かな緑を輝かせている。母を失った娘が見上げる夜空にまたたく星の光は、なんとやさしく美しいことだろう。
書き記され、遺された言葉は、単なる文字ではなく、声となって現在に届けられたのだと思う。原爆の悲劇を伝えることが現代日本の課題のひとつであるとするなら、その悲劇を越えて、平和の祈りへと結実させていくこともまた、私たち読者の使命にちがいない。「祈りの長崎」という言葉にふさわしい、命の記録へのまなざしが、今こそ必要なのではないだろうか。事実そのものだけではなく、その事実への思索と応答とでもいえばいいのだろうか。
事実だけでは拓くことができない未来に向けて、人間の思いが動いてこそ、「平和」という言葉が意味を持ち始めると私は思う。人間の思いを喚起することこそ、文学の、言葉の、大切な力ではないだろうか。
「原爆でむごたらしく死んだ 父母や姉や友だちが 私を生かすために
生命の灯をつぎたしてくれるのか
不思議なエネルギーが
私のやせこけた体に充満する」
(「原爆のうた」福田須磨子)
苦悩を抱えた声が、自身を励ます健気な言葉となって人を生かしているのだ。私たちは文字を読む行為を越えて、生命の灯が絶えてはならないと強く思っている自分に気づく。そこから、思いが動く。祈りが生まれる。
12月には、長崎の被爆をテーマにした映画『母と暮せば』が公開される。歴史は、人の思いがそこに向けられる限りは、風化しない。そして、『ナガサキの命』がこうして十代の読者の手に届けられるのも、「言葉を越える経験をどう伝えうるか」という問いへのひとつの試みだといえるだろう。この一冊の本を読んでいると、吉永小百合さんの朗読が、行間から静かに聴こえてくるような思いにとらわれる。その声に耳を澄ますように、ひとりひとりの作者たちの言葉を大切にうけとめたいと思う。子どもたちの心にも、命の記録へのまなざしが、静かに、でも確かに、広がってゆくことを願いつつ。
はやかわ・あつこ 津田塾大学英文学科教授
「本の旅人」2015年12月号より転載
※便利な定期購読のお申し込みはコチラ