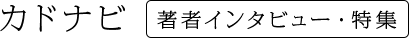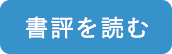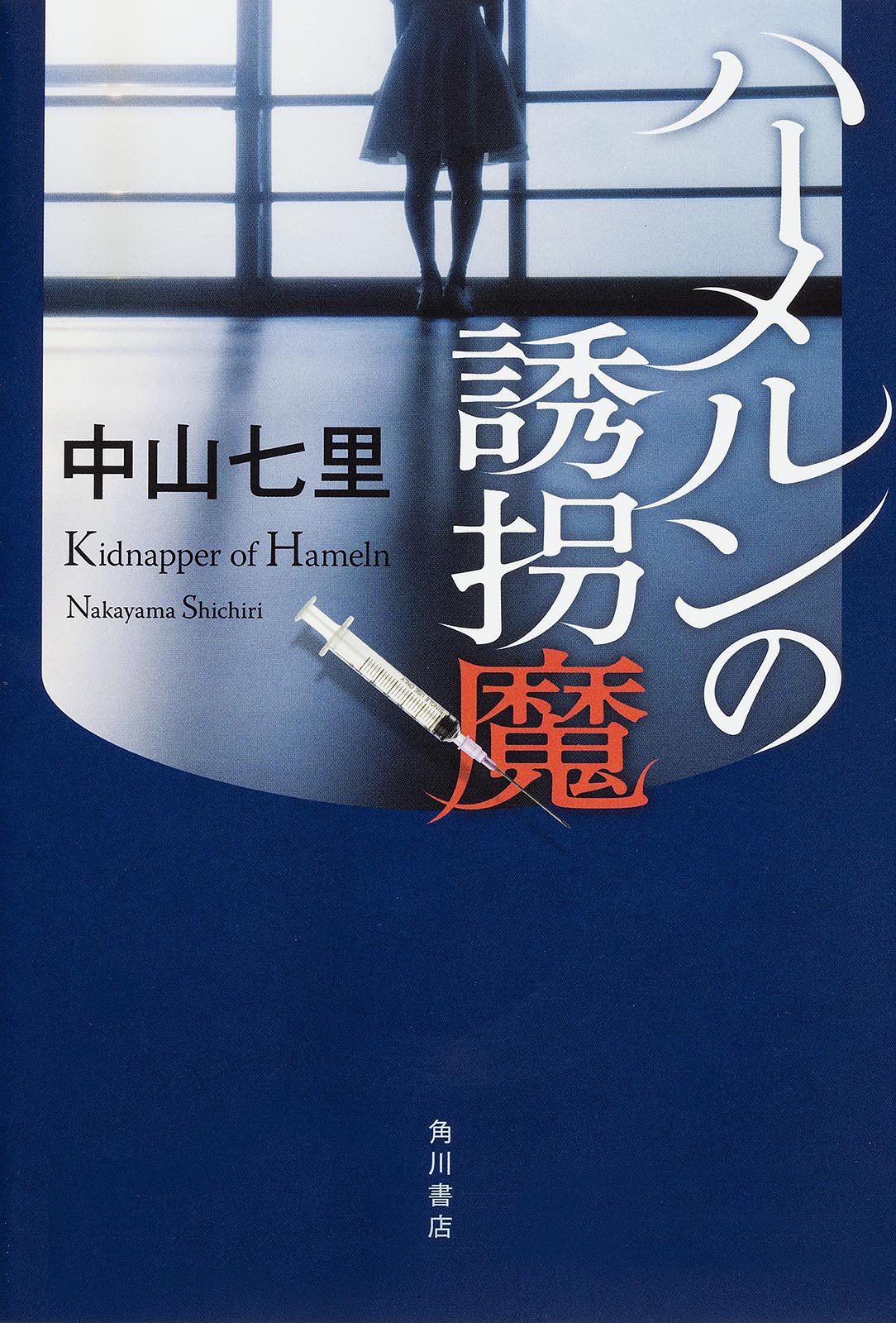

なかやま・しちり
1961年岐阜県生まれ。2009年『さよならドビュッシー』で第8回『このミステリーがすごい!』大賞を受賞。圧倒的なリーダビリティとラストの意外性で話題に。著書は他に『贖罪の奏鳴曲』『切り裂きジャックの告白』『七色の毒』『テミスの剣』『月光のスティグマ』『嗤う淑女』『ヒポクラテスの誓い』『総理にされた男』『闘う君の唄を』など多数。
作家ができることは、事実を広く知らしめること
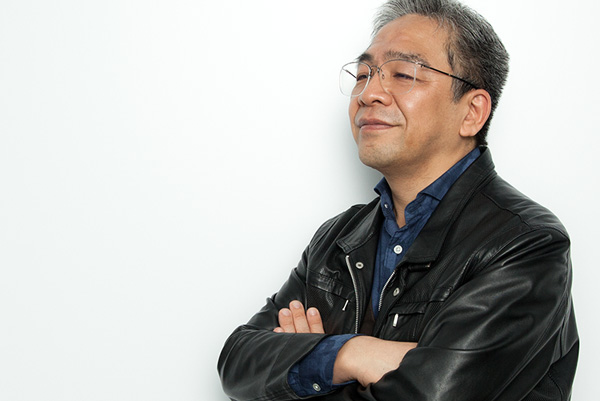
―― 新作は、長篇『切り裂きジャックの告白』、短篇集『七色の毒』に続く、犬養隼人刑事を主役とする作品です。切り裂きジャックとハーメルンの笛吹き男、前作では臓器移植を扱って今回は薬害事件と、長篇二作には共通点がありますね。このあたりは最初から構想されていたことなんですか。
中山 いえ、シリーズ化を考えて書いたことは今まで一度もないんです。幸い前作が好評だったので出版社から続篇のオファーを頂戴して、そのときに改めて過去の有名なダークヒーローを使うというくくりをつけようと考えました。ちなみに現在「日刊ゲンダイ」に連載中の長篇3作目は『ドクター・デスの遺産』といいまして、安楽死の問題を扱ってるんですよ。ただ、『ハーメルンの誘拐魔』には、身内の話も入っています。私の娘が中学1年のときに子宮頸癌ワクチンを打って、その副作用が出るという事件がありました。その直後に私は作家としてデビューしたのですが、その記憶が鮮明に残っていて、続篇の話が出たときにすぐこの話を思いついたんです。私と同じように娘さんがワクチンの副作用で苦しめられた方は判明しているよりもずっと多いはずです。でも、テレビなどでは少ししか報道されない。これまで自分の政治的な意見は極力排してきたつもりなんですけど、今回は特例的に肩入れをしてしまいました。世の中には苦しんでいる人がたくさんいるんだということを知ってほしい。作家に何ができるかといったら、事実を広く知らしめることしかないんです。それにもちろん、皆さんが治って元気になることを祈りたい気持ちもあります。
―― 過去の作品で言えば中山さんは『アポロンの嘲笑』(集英社)で東日本大震災が発生した直後の福島を舞台にされるなど、ときどきの重大事を織り込んで書かれる印象があります。
中山 物書きの仕事の一つは「記憶させること」、もう一つは「皆さんが思っていてもなかなか形にしづらいものを文章化すること」だと思います。テレビは「記録」してくれるんですね。だからこっちは記憶させたい、それをどこまで人の心に刻み付けられるか、ということを考えてやっているということはありますね。
一気読みの悦楽を味わってほしい
―― 記憶と言えば、中山さんは執筆の際、一切取材をされず、ご自分の中から出てくるものだけをお書きになると伺っています。
中山 取材した内容にひっぱられる、ということがあると思うんです。例えば本職の弁護士の方が法廷ものを書こうとしたら、ありえないことは書けない。ところが僕なら門外漢ですから、ありえないことでも書ける。そういう強みがあるんです。物書きとしての僕に必要なのは文章力と構成力、想像力だけなんですよ。その想像力を取材することで削ぎ落としたくない。もっと言うと、本当に取材って必要だろうか、という気持ちもあります。読者の皆さんはノンフィクションが読みたいわけじゃない。それらしい世界に連れていってくれたらいい。そのためのリアリティであり、そのリアリティを生かすための取材じゃないですか。だったら、リアリティのある嘘をつけるなら、取材はいらないだろうと。
―― 今、文章力のお話が出ました。中山さんの武器の一つに、読みやすい文章があると思います。どの作品もスピード感のある読書ができて、途中、停滞するところがないですよね。
中山 とにかく一気読みしてほしい、というのはあります。明日は期末試験だとか、就職面接だ、というときに限って「この本を10ページだけ読もう」と思ったら朝日が昇っていたということがよくあるじゃないですか。そういう経験を私は何度もして現在は物書きになりました。その一気読みの悦楽とか陶酔みたいなものは味わってほしいな、と思います。
―― ただ、文章が読みやすいだけでは、長さのあるものを最後まで読み通させることは難しいですよね。たとえば構成なども、一気読みを意識して作られるんですか。
中山 はい。最初のプロットの段階で「ここは、この台詞から始まる。そして大体25枚目でこうなる。50枚目でこうなる」という具合に原稿用紙25枚ペースで全部話を作るんです。それで最後の台詞とか地の文まで考えて、私のプロットは完成します。だから担当の方にプロットをお渡しした時点で、頭の中では全部完成しています。その文章をダウンロードするだけだから、書いていて詰まることは一切ないんです。楽です。それこそ酒飲みながらでも書けます(笑)。
―― それはアクションなどの動きのある場面でも、尋問とかの静かな場面でも一緒ですか。
中山 そうです。小説にはダレ場とかメリハリがあるじゃないですか。でも、メリハリがあるのは文章の中だけで、書いてる本人は同じテンションです。私は「今日は乗らない」というのが全然ないんです。そういう態度って要は会社員が「今日は乗らないから会社早引けします」って言うようなもんだから(笑)。
「!」の数まで計算されたリーダビリティ

―― 今回の作品でおもしろいのは、語りのペースが変化するところですね。最初は誘拐事件が発生して、ハーメルンと名乗る人物が何を考えているのかわからないために不安がどんどん募ります。物語も空気が淀んだ感じがあります。ところが中盤でそれが変化して、流れがいきなり加速する。そこからは一気呵成に解決までなだれ込んでいきます。このギアチェンジも中山作品の特徴だと思うのですが、やはり書くものによって読ませる速度というのは変えているんですか。
中山 内容の事件性とストーリーによって緩急の付け方は調整しますね。それは「!」の数などでもコントロールできる。例えば『テミスの剣』(文藝春秋)では一つも使っていない。もっと言うと、作品のテーマによって「!」と「?」の個数を決めています。「このテーマなら原稿用紙一枚につき何個にしよう」というように。
―― そこまで決められますか!
中山 今回も、最初のオファーで言われたのは、どんでん返しの凄いもの、ということなんですよね。じゃあ、具体的にはどうしたらいいか。いくつかあるどんでん返しのうち最後のものを効果的にするには、原稿用紙の最後から数えて何枚目ぐらいに入れたほうがいい。じゃあその前のどんでん返しはそこから原稿用紙何枚ぐらい前だろう。その間にはどういう台詞とどういう地の文が必要か。そこで考えたのが、この箇所では地の文と台詞の比率を4対6にするのが最適だろうと。そうやって、地の文と台詞の長さを計算していったんです。車で走っていって急に風景が変わる、というようなことがあるじゃないですか。その体験がどのくらいのスピードだと効果的かはわかる。それを文章化しているんです。
―― おもしろいです。内容面で言うと、今回は誘拐事件ということで身代金受け渡しが行われますね。あの場面もオリジナルのアイデアが効果的に使われていたと思います。
中山 誘拐もので言うとエポックメイキングなのは黒澤明の「天国と地獄」だと思うんですけど、一番の山場はやっぱり身代金の受け渡しですよね。だからそこがうまいこと書けていたら大抵の誘拐ものというのは成功するはずなんです。
―― その身代金奪取に関するものと、もう一つ大きなトリックがありますね。『切り裂きジャックの告白』のときも意外な犯人に意外な動機というのがありました。中山作品の特徴は、記憶に残るトリックを一つ以上必ず埋め込むということではないかと思います。
中山 トリックは常に三十いくつ頭の中に入ってるんですよ。それをオファーが来た内容に合わせてはめ込んでいくだけです。それが端的に表れたのが『七色の毒』でした。これは頭の中にあるトリックをどんな順列、組み合わせにしたら一番効果的か、実験をした作品でした。なぜそれができるのかというと、私がミステリの古典を死ぬほど読んでいるからなんですよ。私が小学生のころはまだクイーンもクリスティーも存命で、年に一回は新作が出てましたからね。その読書体験がDNAに刻み込まれていると思っています。
―― 作家としての血肉になっているわけですね。
中山 そうです。『切り裂きジャックの告白』の依頼をいただいたときは、すぐに横溝正史さんのおどろおどろしさと森村誠一さんの社会派をミックスしようと思いつきましたよ。
―― 1970年代の角川文庫を代表するお二人ですか。
中山 KADOKAWAさんに最もふさわしい作家といえばそのお二人ですからね。
刑事犬養隼人シリーズ好評既刊
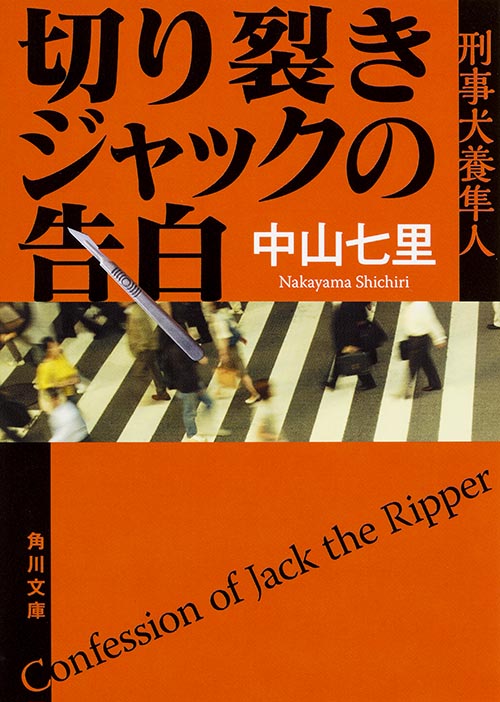
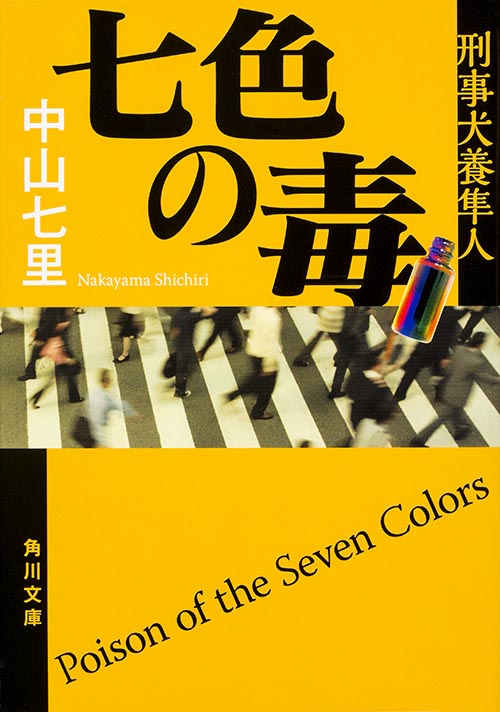
取材・文|杉江松恋 撮影|澁谷高晴
「本の旅人」2016年2月号より転載
※便利な定期購読のお申し込みはコチラ