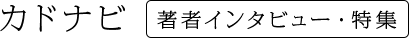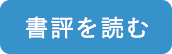むれ・ようこ
1954年東京都生まれ。日本大学藝術学部卒業。数回の転職を経て、78年、本の雑誌社に入社。84年、『午前零時の玄米パン』でデビュー。デビュー作が評判となり、専業作家に。そのほかの著作に、大人気シリーズ「無印物語」「れんげ荘」をはじめ『かもめ食堂』『三人暮らし』『欲と収納』など多数。
今になって「ご近所さん」という感覚が分かってきたんです

―― 新刊『うちのご近所さん』の主人公マサミは就職して3年経った時には「家を出よう」と決意したこともあったし、おつきあいした男性もいなかったわけではないけれど、なんとなく機会を逸しているうち、40歳の今まで実家に居ついてしまった女性で、独身・実家暮らしの自分はいろいろと身につまされました。
群 そうでしたか。私は、子どもの頃からわりと引っ越しの多い家で育ったんですね。会社に勤めて、ひとり暮らしをするようになってからも2回契約を更新すると引っ越すみたいなことをやっていたので〈ご近所さん〉という感覚が全然なかったんですけど、今のところに住むようになってだいたい20年経つんです。都心のマンション暮らしで、まさか20年も同じところに住むとは思ってもいなかった。マンションとはいえ住み続けていると、町内の様子が変わったり、新しい方が引っ越してこられたり、お子さんが生まれたりとかね、いろんなことがあるわけです。地方と違ってそこまで密着したおつきあいがあるわけじゃないけど、会ったら挨拶する、立ち話するみたいな関係性がある中で、顔見知りの方に変化があったりすると、ああ、なるほどねと思ったりして。それこそ引っ越した当初から猫つながりで知り合った方とかが亡くなったり施設に入られたりすると、時のうつろいを感じるというか、他人なんだけど心情的に訴えるものがあるじゃないですか。ああ、ご近所さんっていうのはこういう感じなんだなあと今になって強く感じたんですね。
―― お父様に引っ越し癖があったとか。
群 そうなんです。飽きっぽい父親の気まぐれで3、4年に一回は東京都内を転々と。子ども心に、また引っ越しか、面倒くさいなあと思っていました。小学校4年生の時にはひと駅隣に引っ越したんですけど、小学校でも学区によってランクがあるじゃないですか。それまでいた小学校ではすっごい成績がよくて、この私が神童と呼ばれていたんですけど、転校したら周りがとてつもなくできる子ばっかりで凡人以下になっちゃって。ひと駅違うだけでこんなに違うんだ、これからは目立たないように生きていこうって、初めて世の中を知ったのはあの時だったかも(笑)。
―― 『うちのご近所さん』の舞台も、その中のどこかだったりするんでしょうか。
群 具体的にどこと決めているわけではないですが、小学校4年生の時に住んだ街のイメージがあるような気がしますね。練馬なんですけど、当時はうちの父親が一番羽振りがいい頃で、それまでで一番いい家に住んでいたんです。出版社の役員の方が自宅とは別に持っていた家で、庭はドッジボールができるくらい広くて、外観はコンクリート打ちっぱなし。和室が一部屋ある以外は全部フローリング。50年以上前なのにトイレは洋式だし、全室エアコン完備。北欧風のオシャレな家で、周りも会社役員の方が住んでいるようなお屋敷町でした。でも道一本裏手に行くと誰が住んでいるのかもわからないような小さな家がたくさんあって、私の中で住宅街といえば、あの頃のあの街の風景が浮かぶんですよ。それこそこの小説に出てくるギンジロウみたいな、通学路で仁王立ちしてる嫌われ者のおじさんもいたし、白塗りのセンダさんみたいな滅多に姿を見たことがない人もいて、これを読んだちょっと年上の編集者の方がすごく懐かしい感じがすると言ったのも、そういう風景にどこかノスタルジーを感じるからかもしれませんね。
―― ご近所づきあいということで言えば「重箱入りでまわってくる手作りのおはぎ」なんかも「あったあった」とうなずいてしまいました。
群 うちもそうでしたから。ああいう時はおはぎに決まってましたよね。母が重箱に詰めて持っていくのもおはぎだったし、ご近所さんからもおはぎ以外がまわってきたことはなかった。それも売ってるのとは違う、巨大なおはぎでね。今は消臭スプレーしちゃうからどんな家もにおいがしないけど、昔はそのうちのにおいってあったじゃないですか。小学生のマサミがセンダさんが紙に包んで握らせてくれた干菓子が食べられなかったのも、自分のうちとは違う、よそのうちのにおいがしみついていたからなんですよね。
―― 噂好きのヤマカワさん、新興宗教にハマった勧誘熱心なセトさん……連作短編に登場するご近所さんたちも、どんな街にもひとりはいそうな感じがします。
群 どこの町内にもうるさいおじさんと面倒くさいおばさんがいて、きっと一定の比率で分布してるんじゃないですか。私がまだマンションを転々としていた頃、なんか法事が多いところだなと思ったら、そこのマンションには私以外全員、宗教関係の方が住んでいたなんてこともありました。どうも私の隣に住んでいる奥さんが全員を引き入れたらしくて、勧誘がしつこくてね。だから具体的なモデルがいるわけじゃないけど、行き当たりばったりに書いていくうち、そういう経験を思い出すんでしょうね。今のマンションに引っ越した時も、ご近所にちょっと困った子がいて、うちの猫をBB弾で狙うんですよ。その子のことなんて、お母さんのお腹の中にいる時から知ってますからね。ちっちゃい頃から凄まじい声で泣く子で、それこそ小説に書いた〈絶叫の館〉みたいな感じ。さすがに最近は落ち着いたなと思っていたら、おととしの夏だったかな。窓を開けたらものすごい異臭がして、なんだろうと思ったら、その子がベランダで制汗スプレーをぶわーっと全身に(笑)。顔は知ってるけど、直接しゃべったことはないですよ。ないけど20年いると成長していくのがわかるじゃないですか。ちょっとくらい腹の立つことがあっても、あの子がやってるんだと思えば許せたりして、短期間ではわからない人間関係があるんですよね。
―― 噂好きのヤマカワさんにしても、煙たがられるだけじゃなくて「あの人に聞けばわかるかも」と重宝がられていたりもして。
群 ああいう人を描くのは楽しいですね。宗教にはまったく興味はないけど、セトさんが太鼓叩いて踊りまくっちゃったりとかね。宗教のせいでその人が絶対にやりそうもないことができちゃったりするのって不思議じゃないですか。不思議な人を描くのはやっぱり楽しいですよ。マサミにしても、適齢期には〝あそこのお嬢さん、いつお嫁に行くのかしら〟と言われていたのが、ある程度の年齢になると〝偉いわね、親御さんの面倒をみて〟というふうにご近所さんの見る目が変わってくるし、あの頃は子どもだったからわからなかったけど、今思えば、ということもありますよね。だからたまに実家に帰ってきて誰かが変化していたのを描くんじゃなくて、自分も変化するけれども、周囲の人も変化していくという状況を描いた方がよりリアリティがあるなと思ったんです。
―― あの頃あった大きな家が今ではマンションに変わっていたり、一章の中で30年余の時が流れているのはそういう理由なんですね。ご近所さんとの関係も、あの頃と今とではやっぱり変わってきたりするんでしょうか。
群 今って個人主義が極まっちゃって、隣に住んでいる人の顔を知らないって人もたくさんいるでしょう。若い編集者の方に聞いたら、すべて管理会社を通してやりとりするから大家さんにも会ったことないって言うんですよ。でも一方で町内会に若いご夫婦が積極的に参加して子育てのアドバイスをもらったりとか、ご近所づきあいが復活してきてる感じもするんですね。昔と違って、自分からしゃしゃり出たりはしないけれど、頼まれたらできる範囲のことはするみたいな程良い距離感を、みんな、勉強してきてると思うんです。マサミも親がもっと年をとれば、この先いろんな問題がでてくるでしょうし、そういう関係性があった方がお互いラクになるんじゃないかなって思いますね。
女の人がひとりで生きていくこと 女友達がいれば大丈夫

―― 群さんにも、そんな頼りになるご近所さんっていますか。
群 今のマンションに引っ越したのは、友人で女優のもたいまさこさんが〝隣の部屋が空いたから引っ越して来ない?〟と声をかけてくれたからなんです。それまで放浪の日々だったのに居心地がいいせいか、あれから二十年も経ってしまいました。隣に住んでるのが他人だったらまた違ったかもしれないけど、顔見知りで友達だと、何かあったら助け合う互助会みたいになってますね。私もフリーランスだし、将来どうなるかわからないじゃないですか。別に貯金がたくさんあるわけではないし、身内もいないし。身内がいるからどうってこともないんでしょうけど、でもまあ、ひとりでずーっとやってきた女の人たちのことをいろいろ考えていると、女友達がいれば全然大丈夫、全然オッケーだなって思いますね。
―― やっぱり、そうですか。
群 はい。やっぱりそうです(笑)。
―― 思わず身を乗り出してしまいました(笑)。
群 もたいさんとのつきあいは22、3年になるのかな。長いですよね。『やっぱり猫が好き』というドラマが好きで、当時「週刊文春」でテレビのコラムを書かせてもらっていたので、そこで取り上げたら、それが一番初めに出たテレビ評だったらしくて、もたいさんが女子大でやる対談のゲストとして呼んでもらったのが出会いでした。初対面だったし、すごく緊張してたと思うんだけど、ざっくばらんに接してくださって、その日のうちに意気投合、ごはんを食べに行ったんです。その時に小林聡美さんも来たんじゃなかったかな。ご近所さんになってからは〝お醤油貸して〟みたいな間柄になって。もたいさんが猫ちゃんを飼っていた頃は、家を空ける時は私がずっと預かっていましたから。私も猫を拾ってからは、猫同士いろいろあったりして。
―― じゃあ『かもめ食堂』も、おふたりのご近所づきあいから生まれたというか。
群 そうですね。もたいさんの事務所の社長がある日、トントンとうちのドアをノックして、小林さんとNHKの番組でフィンランドに行ったらとても良かった、フィンランドを舞台にした映画をつくりたいので、私に原作を書いてくれないかって。最初に言われたのは小林さんともたいさんと片桐はいりさんが出て、フィンランドで食堂をやる話ということだけだったんです。経営者が年下というのがピンとこなくて、年上のもたいさんを主人公に70枚くらい書いたのかな。そうしたら今度はもたいさんがトントンッてうちに来て、主人公は自分より聡美ちゃんの方がいいと思うんだよね、って。
―― 『かもめ食堂』がエポックメイキングだったのは、男性が「いつかリタイアしたら蕎麦を打ちたい」と夢見るように、女性にとっていつかたどりつきたい夢の城を具体的に描いてみせたところだと思うんですよね。
群 そう思われちゃうと、ちょっとまずいんですけどね(苦笑)。あの小説の三人も、実は親を捨て国を捨てフィンランドに行ってるし、現実ってそういうものだと思うから。
―― そこに行けば夢がかなうガンダーラみたいな場所はない、と。
群 そう。やっぱりね、何か捨ててるから何かがあるんですよ。
―― 群さんが作家デビューしたのって、日本がバブルの熱狂に踊っていた頃だったのに、群さんのベクトルって当時から真逆というか、地に足が着いてましたよね。どうして当時から一貫して半径500メートルの日常を描いてきたのでしょう。
群 それ以上広げると面倒くさいから(笑)。自分の目が届く範囲のことしかやらない。ドラマチックに盛り上げたりしないのも、やっぱり日常の中に面白さとか悲しみとかそういうものがあると思ってきたからじゃないですか。ずいぶん前に小学校の同級生にバッタリ会った時にも言われましたよ。〝いつも自分たちのことをじーっと見てる気がして怖かった〟って。自分ではそんなつもりはなかったけど、渦に入るより、渦に集まる人を観察する方が面白いと思ってきた人間なんです。
―― 時代や流行にあおられることなく、なぜ群ようこという作家は平熱でいられるのかなと思っていましたが、その秘密が垣間見えたような気がします。語り口こそひょうひょうとしているけれど『かもめ食堂』にしろ「れんげ荘」シリーズにしろ「自分のやりたいことがわかっている人の強さ」を感じます。
群 デビュー当時から、月に何本とか自分で枠を決めて、仕事を断ったりしていたので、すっごい生意気だって言われましたよ。 〝せっかく仕事を振ってやったのに何だ!〟って怒られたりもしたけど、やりたくない仕事もありましたし、これ以上は自分でできないというのもわかってましたから。
―― 仕事を断って、何をしていたんですか。
群 あの頃は、麻雀かな。
―― え、麻雀ですか!?
群 いいですよお、麻雀は(笑)。あんなによくできたゲームはない。母親が体調を崩してからしばらく遠ざかっていたんですけど、最近また勉強し直してるんです。若いお嬢さんだと時間ができたらもっと有意義なことをしようと思うんだろうけど、あの頃の私にとって最優先でやりたいことが麻雀だった(笑)。自分なんてね、磨いたってそこまで光るもんじゃなし。流行や世の中の評価みたいなものってめまぐるしく変わりますから、そんなものに左右されていたら、自分がどうなるかわからないじゃないですか。世の中に合わせていればラクなのかもしれないけど、自分にそぐわないものもあるだろうし、大事なのは〝世の中はいいから、あなたはどうしたいの?〟ってことなんだと思うんですよ。最初からそれをわかってる人はいないし、迷いながら見つけていけばいいんじゃないですか。
―― 群さんが描く、30代、40代になってからまた新しく人生を始める主人公たちに励まされてきた読者は少なくないと思います。
群 最近、友達が新しい仕事を始めたんです。彼女、私よりひとつ上なんですけどね。最初は迷っていたんだけど、やりなよ、やりなよって。そうすると何かやろうと思った時に必ず彼女の役に立てる人がいるんですよ。ずっと主婦をやってきた人は料理で助けてあげたり、仕事してきた人は人脈で助けてあげたり、何かしら道をつけてあげられる。だから女友達がいれば、大丈夫。いつだって始められるし、遅すぎることはないと思っています。
取材・文|瀧 晴巳 撮影|ホンゴユウジ
「本の旅人」2016年3月号より転載
※便利な定期購読のお申し込みはコチラ